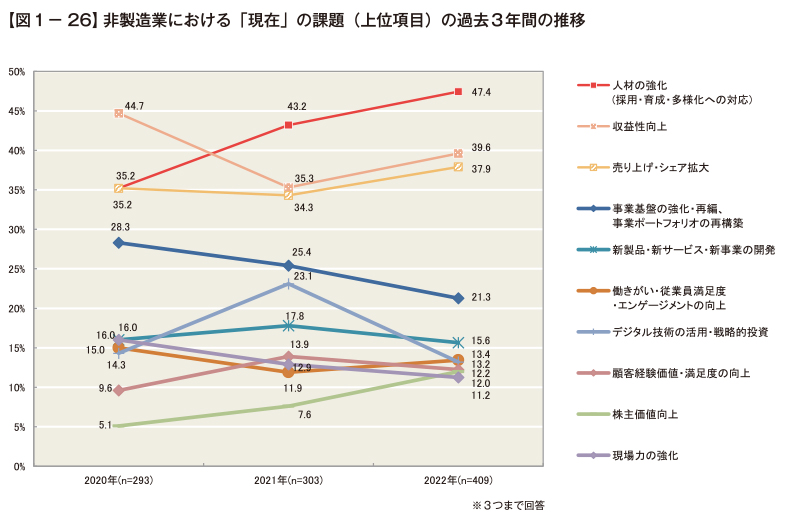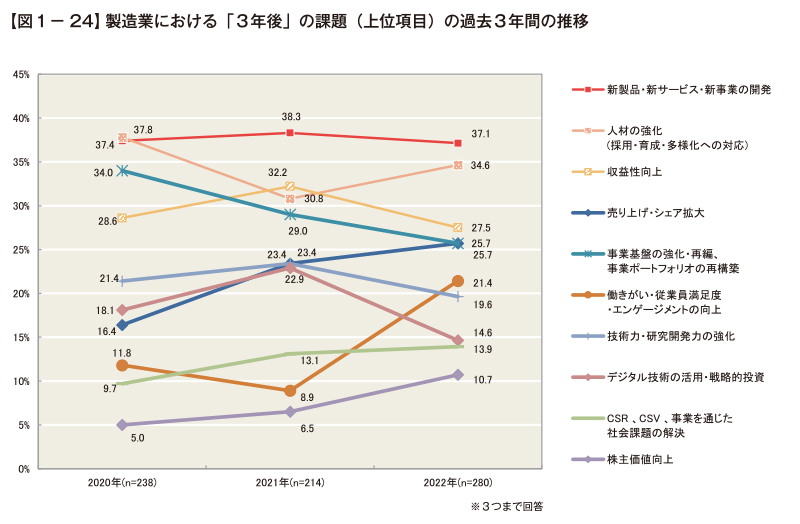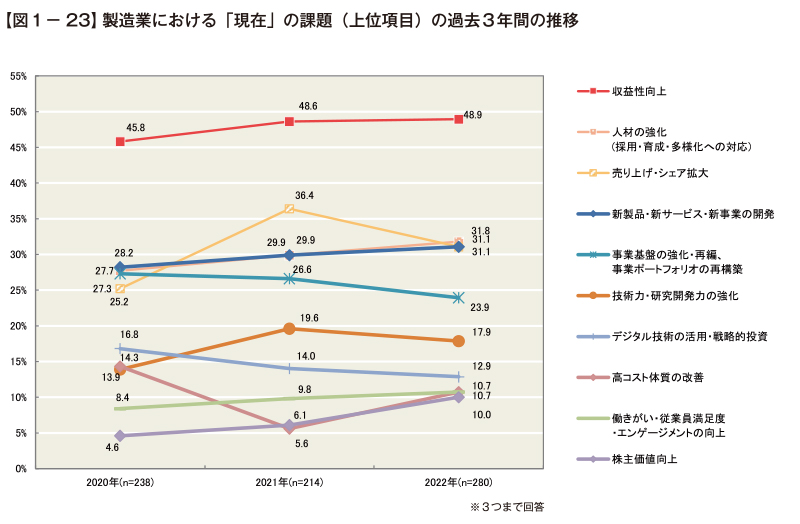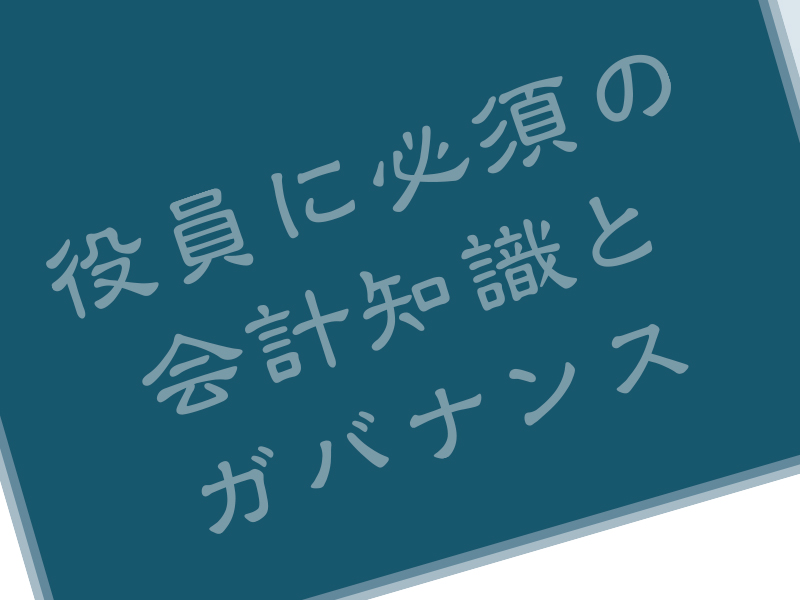
日本能率協会の経営情報誌『JMAマネジメント』の誌面から「役員に必須の会計知識とガバナンス」全7回の連載をお届けしてまいります。
本連載は監査法人の仕事に精通する伊藤浩平氏(公認会計士・税理士)、ならびに、製造業の利益管理やIT活用に精通する経営コンサルタントの本間峰一氏(中小企業診断士)に執筆いただいた全7回の連載です。
ACEコンサルティング株式会社 公認会計士、税理士
伊藤浩平 氏
ここ数年、わが国を代表するような大企業において不正会計事件が起こりました。そのなかで、監査に携わる監査法人や公認会計士(以下、「監査人」と略します)が、不正会計をなぜ発見できなかったのか、というような議論が起こりました。今回はこうした議論も踏まえ、前回に引き続き公認会計士監査に関するトピックスを解説します。
監査意見
公認会計士監査では、企業が作成した財務諸表の会計監査が終了したならば、監査報告書で監査意見が表明されます。この監査意見には次の4パターンがあります。
- 1)無限定適正意見 財務諸表(計算書類を含みます)が会計基準に従って適正に作成されたことを、監査人が認める場合に表明されます。
- 2)限定付適正意見 財務諸表に重要な虚偽表示があるが、その範囲は広範でない場合、また十分かつ適切な監査に必要な情報(監査証拠)を入手できず、財務諸表に重要な虚偽表示の可能性があるが、その影響は広範囲でないと監査人が判断する場合に表明されます。
- 3)不適正意見 十分かつ適切な監査証拠を入手したが、財務諸表の広範に重要な虚偽記載が存在すると監査人が判断する場合に表明されます。たとえば、監査人が、貸付金の回収可能性から見て、当該企業の貸倒引当金の計上金額が大幅に不足していると判断した場合などに表明されます。
-
4)意見不表明
十分かつ適切な監査証拠を入手できず、財務諸表に重要な虚偽表示の可能性があり、その影響が広範囲であると監査人が判断する場合に表明されます。たとえば、当該企業が、監査人に対して貸付金の回収可能性を判断するための十分かつ適切な監査証拠(たとえば貸付相手の財務内容を示す資料)を提供しえない場合などに表明されます。
上場企業の財務諸表に対する監査意見が「不適正意見」または「意見不表明」の場合、東京証券取引所の上場廃止基準に抵触します。また非上場企業で会社法に基づく会計監査人監査のみを依頼している場合であっても、当該企業に融資を行っている金融機関は、年度決算の監査結果を気に掛けるものであり、監査報告書の提示を求めることも多くあります。そこでの監査意見が「不適正意見」や「意見不表明」の場合、財務諸表に対する信頼性がないと監査人が表明しているのと同然であり、取引金融機関が当該企業から融資を引きあげる原因ともなりえます。
公認会計士監査では、監査人がいきなり「不適正意見」や「意見不表明」を表明するわけでなく、事前に経営者との間で監査意見に関する協議が行われるのが通常です。こうした監査人との協議の場を通じて、どのようにすれば「不適正意見」や「意見不表明」が避けられるのかを検討します。先に挙げた「意見不表明」の事例でいえば、貸付相手の財務内容を直接的に示す財務諸表のような直接的証拠を示せない場合であっても、貸付相手の財務内容が健全であると推測できるような間接的証拠をいくつか提供すること、あるいは貸倒引当金計上額を増額させるなど、より慎重度を高めてリスクに備える、保守的な会計処理に変更することにより、「意見不表明」が回避され「無限定適正意見」に変わるかもしれません(監査人は実態把握が困難な状況では保守主義の原則による判断をします)。
期待ギャップ
ところで公認会計士監査での監査意見が「無限定適正意見」とはどのような状態を示すのかに関して、一般的な財務諸表利用者が期待していることと、監査人が想定していることとの間には差異があるといわれ、「期待ギャップ」と呼ばれます。一般的な財務諸表利用者は、無限定適正意見が表明されたということは、対象企業の財政状態・経営成績は健全であり、重大な会計不正行為はないと監査人が判断した、と捉える傾向にあるようです。
これに対して監査人は、無限定適正意見の表明は、財務諸表が会計基準に従って適正に作成されたと評価しているにすぎず、そこに財務健全性の評価は一義的には含まれない、と想定しています。また重大な会計不正行為に関しては、(公的に定められている)監査基準に準拠して実施した監査手続きの範囲においては検証しているが、そもそも公認会計士監査には限界があり、重大な会計不正であっても公認会計士監査では発見できないことがありえる、と感じる監査人が多いかと思われます。
公認会計士監査の限界
山浦久司・明治大学大学院教授は、『監査論テキスト〔第六版〕』(中央経済社)の中で公認会計士監査には次のような機能的限界があると指摘しています。1)監査業務には、費用的・時間的制約があり、記録全部の監査(精査)ができない。
2)監査人は企業側の管理体制(内部統制)に依存せざるをえず、その良し悪しを勘案しながら監査の重点や抜き取り検査の範囲を決めていくが、内部統制が経営者の干渉や従業員の共謀などで機能しなくなり、結果として、財務諸表の虚偽表示を発見できない。
3)たとえ精査ができても、入手できる監査証拠は会計記録自体と伝票や証しょう憑ひょうなど、取引結果を示す間接証拠がほとんどであり、取引の存在や実態について絶対的というよりは、せいぜい合理的と思われる程度の推論的な基礎しか得られない。
4)たとえ確証的な証拠が得られたとしても、たとえば貸倒引当金の見積もりなどに見られるように、会計処理は将来事象に対する判断の所産であることが多く、せいぜい企業側が行った将来判断が、監査人の立場からも合理的に判断できる、といった程度にしか結論を形成できない。
筆者は、会計不正事件について、監査人とは異なる立場から調査する業務をしていますが、公認会計士監査が見破れなかった最近の会計不正事例では、単に公認会計士監査の機能的限界のみでは説明が済まされず、経営者の誠実性への過信、対象企業の業務や会計の仕組みに対する理解不足など、監査人が反省すべきケースもあるように思えます。
GC注記(継続企業の前提に関する注記)
監査対象企業の財務健全性の評価に関しては、監査基準の改訂などにより、2003年3月期から企業が将来にわたって活動を継続するという前提(継続企業の前提)に関して経営者と監査人が検討を行うことが義務づけられました。その結果、たとえば債務超過状態であり、その回復の見通しがはっきりしないなど、事業継続に重大なリスクがある、と監査人が認めた場合、当該企業に「継続企業の前提に関する注記」(Going Concern:継続企業の頭文字をとって「GC注記」とも略称されます)を財務諸表に開示するよう指導し、監査報告書にも追記情報として、GC注記が存在することをあらためて記載します。こうしたGC注記が記されている場合、たとえ監査意見が無限定適正意見であろうとも、監査人は当該企業の財務健全性に関して否定的に判断している、と考えるべきです。ただし、GC注記が付されているからといって、監査人は、直ちに当該企業が破綻すると判断しているわけでなく、事業継続ができなくなるリスクが通常の企業よりも高いと評価される、という注意喚起情報として理解すべきでしょう。
また、GC注記の記載には、取締役や監査人にとって、万一、当該企業が経営破綻した場合、経営状態の悪化を事前に適切に開示しなかったのではないか、という株主などからの訴訟リスクやクレームを軽減させる側面もあります。
次回は「税務と連結——さまざまな企業決算」について解説します。
本コラムは2016年5月の『JMAマネジメント』に掲載されたものです。