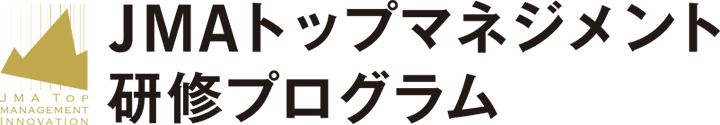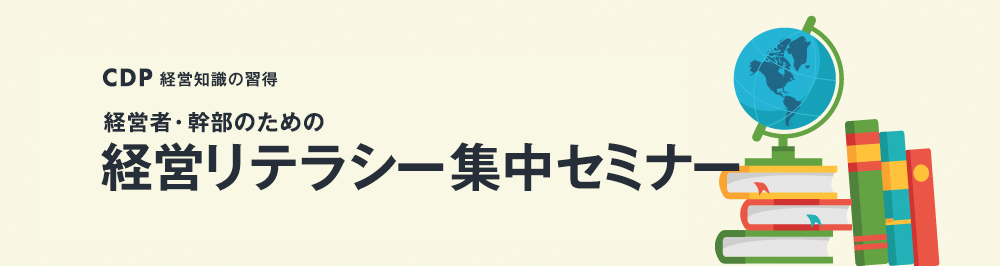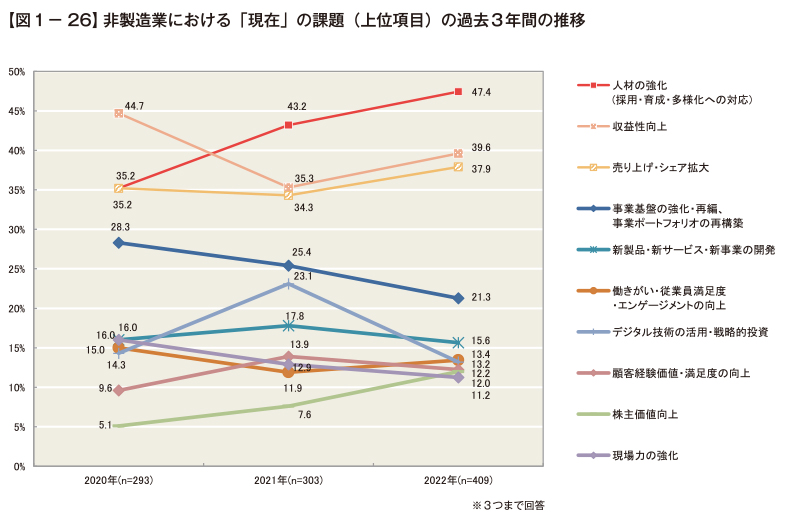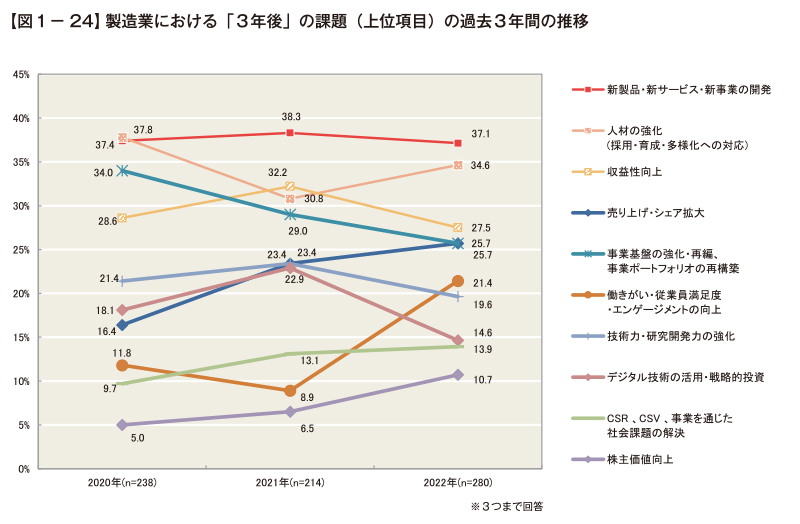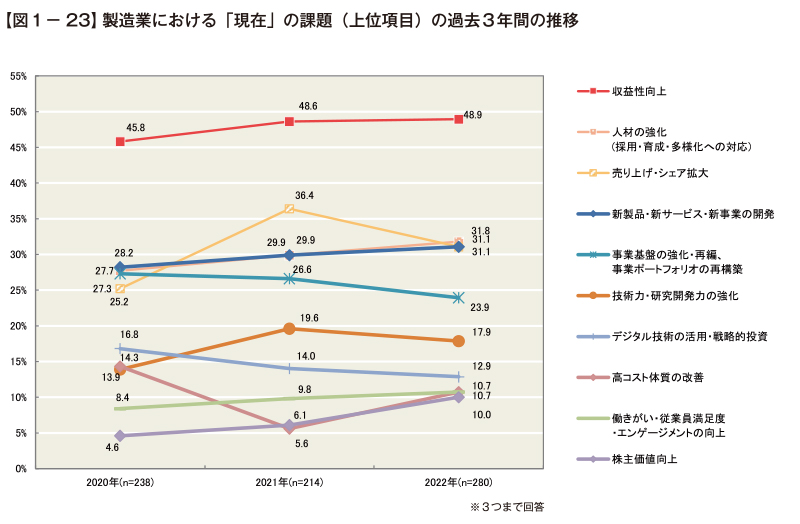経営の必須知識を3日間で集中的に学ぶ
CDPの3セミナー「法務・企業統治セミナー」「戦略財務・会計セミナー」「経営戦略セミナー」のエッセンスを3日間に集約したプログラムです。企業経営の舵取り役として是非ともおさえていただきたい要素が凝縮されています。講師のレクチャーのみならず、参加者同士のディスカッションも配し、明日の経営に役立つ実践的な内容となっています。忙しくて研修の時間が取りづらい経営者・役員の方、遠方でなかなか研修に参加できない方におすすめするプログラムです。
ねらい
- 経営者に必須の「法務・企業統治」「戦略財務・会計」「経営戦略」のエッセンスを集約し、短期集中で学ぶ。
- 新任役員、将来の役員候補として、国内外子会社への経営幹部赴任後すぐに実践できる知識を身に付ける。
- 講義だけでなく、他社参加者との討議・交流を通じて多くの気づきを得る。
セミナー概要
- セミナー名
- 経営者・幹部のための経営リテラシー集中セミナー
- 会 場
- 日本能率協会研修室(東京都港区芝公園3-1-22)
- 会 期
-
3日間 通い
- 第40回
2024年6月19日[水]〜21日[金]
- 第41回
2024年8月7日[水]〜9日[金]
- 追加開催
2024年10月29日[火]~31日[木]
- 第42回
2024年11月26日[火]〜28日[木]
- 追加開催
2025年2月12日[水]~14日[金]
- 第43回
2025年3月5日[水]〜7日[金]
- 第40回
- 定 員
- 36名
- 対 象
- 社長、取締役、執行役員、幹部
- 受講料
-
- 日本能率協会 会員
379,500円(1名/税込)
- 会員外
429,000円(1名/税込)
- 日本能率協会 会員
講師
※順不同 ※敬称略 ※2024年度登壇予定
法務・企業統治 (各回お一人の講師が担当します。)

髙木 弘明 レイサムアンドワトキンス外国法共同事業
法律事務所
弁護士
2001年、 東京大学法学部第一類卒業。2002年、弁護士登録(第一東京弁護士会)。2005年、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師。2008年、米国シカゴ大学ロースクール卒業(LL.M.)。2009年、米国NY州弁護士資格取得。2016年、学習院大学法科大学院特別招聘教授。上場会社の企業法務全般、M&A/海外M&A、当局対応/危機管理、消費者法制、税務などを取り扱う。2009年から2013年まで、法務省民事局参事官室に出向し、平成26年会社法改正の立案を担当するとともに、同局商事課を兼務し商業登記等を併せて担当。
〈主な著書〉「改正会社法下における実務のポイント」(商事法務、2016年)

飛松 純一 外苑法律事務所
パートナー弁護士
1996年、東京大学法学部第一類卒業。1998年、弁護士登録(東京弁護士会)。2003年、米国スタンフォード大学ロースクール卒業(LL.M.)。2004年、米国ニューヨーク州弁護士登録。2006年、森・濱田松本法律事務所パートナー。2010年、東京大学大学院 法学政治学研究科 准教授。2016年、飛松法律事務所(現 外苑法律事務所)開設。上場・非上場企業の企業法務全般、企業間紛争・国際商事紛争、M&A、国際商取引案件などを幅広く取り扱うとともに、各種企業の社外役員や官公庁の研究会等の委員も数多く務めている。Chambers Global、Legal 500等の国際的な弁護士ランキングにおいて、日本を代表する弁護士の1人として選出されている。
〈主な著書〉「国際商事仲裁の理論と実務」(共著、丸善雄松堂、2016年)
戦略財務・会計

西山 茂 早稲田大学
大学院経営管理研究科
(早稲田大学ビジネススクール)
教授
早稲田大学政治経済学部卒。ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA修了。監査法人ト-マツ、(株)西山アソシエイツにて会計監査・企業買収支援・株式公開支援・企業研修などの業務を担当したのち、2002年より早稲田大学。2006年より現職。学術博士(早稲田大学)。公認会計士。上場公開企業の社外役員を歴任。主な著書に、『企業分析シナリオ第2版』『「専門家」以外の人のための決算書&ファイナンスの教科書』(以上、東洋経済新報社)、『ビジネススクールで教えている会計思考77の常識』(日経BP社)、『戦略管理会計改訂2版』(ダイヤモンド社)等がある。
経営戦略 (各回お一人の講師が担当します。)
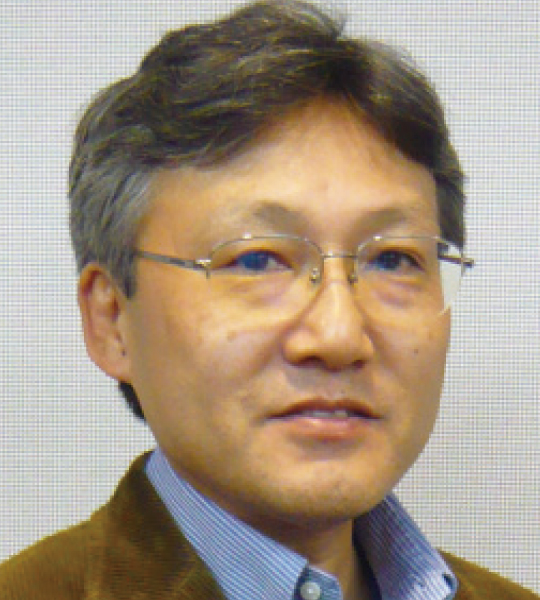
岡田 正大 慶応義塾大学
大学院経営管理研究科 教授経営学博士
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。株式会社本田技研工業を経て、修士(経営学、慶應義塾大学)取得。戦略コンサルティングのArthur D.Little(Japan)社を経て、米国MuseAssociates社(代表:梅田望夫)フェロー。米国オハイオ州立大学にて1999年Ph.D.(経営学)を取得し、慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師に。准教授を経て現在教授。経済産業省新中間層獲得戦略研究会、同省BOPビジネス支援センター運営協議会、同省アフリカビジネス研究会、同省中南米市場獲得における基礎的調査に係る有識者意見交換会にて委員を務める。

菅野 寛 早稲田大学
大学院経営管理研究科
(早稲田大学ビジネススクール)教授
東京工業大学工学部卒。同大学院修士課程修了。㈱日建設計に勤務した後、米国カーネギーメロン大学にて経営工学修士(Master of Science in Industrial Administration)取得。
その後、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)に入社し、十数年間、日本およびグローバル企業に対してさまざまなコンサルティング・サービスを提供。2008年より一橋大学大学院国際企業戦略研究科(一橋ICS)教授。2016年より現職。

淺羽 茂 早稲田大学
教授 博士(経済学)東京大博士
Ph. D.(management)UCLA
1990年 学習院大講師、助教授、教授
2013年 早稲田大学教授
(2016-2020年 早稲田大学ビジネスクールDean)
2015-2017年 組織学会会長
2016年 日本甜菜製糖株式会社外取締役
2017年 沖電気工業株式会社外取締役
専門 : 経営戦略、産業組織
研究トピック : 企業間の競争と協力、模倣、ビジネスモデル、イノベーション、コーポレートガバナンス、ファミリービジネス等
参加者の声
- 法務・企業統治、財務・会計、経営戦略3日間のいずれの講師もとても分かりやすく説明してくださり、よく理解できた。
- 一般論の講義ではなく、実例から本質的な論点での講義やディスカッションが中心である点がよかった。
- 異業種の方々、またそれぞれ得意な領域が異なる中でのディスカッションは、新たな気づきが多かった。とても質の高いセミナーであると感じている。
- 短期集中プログラムであるが、事前課題で予習することにより、経験の少ない私でも当日の説明のポイントがわかり、深く理解することができた。
- 全体的に3日間に経営リテラシーとして必要なことが凝縮されており、今後の研鑽のためにも非常に良い機会となった。