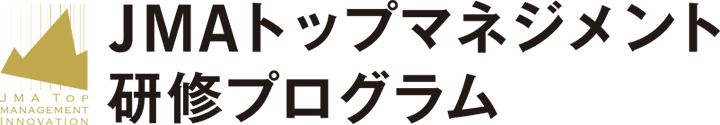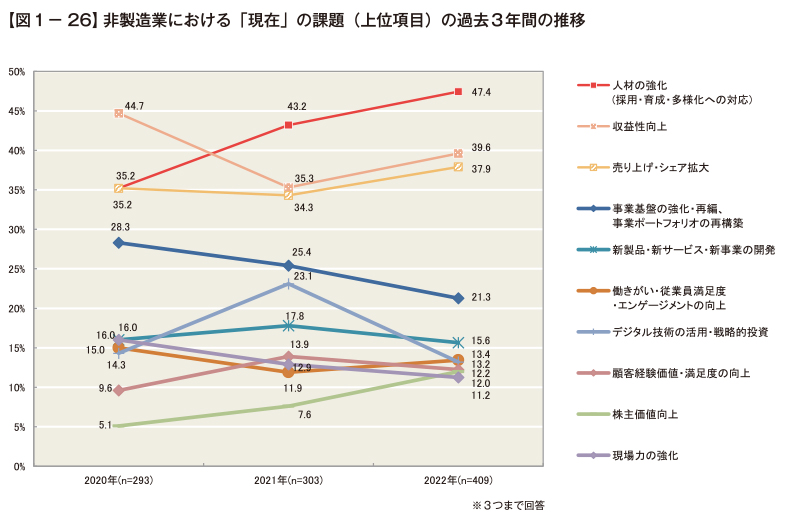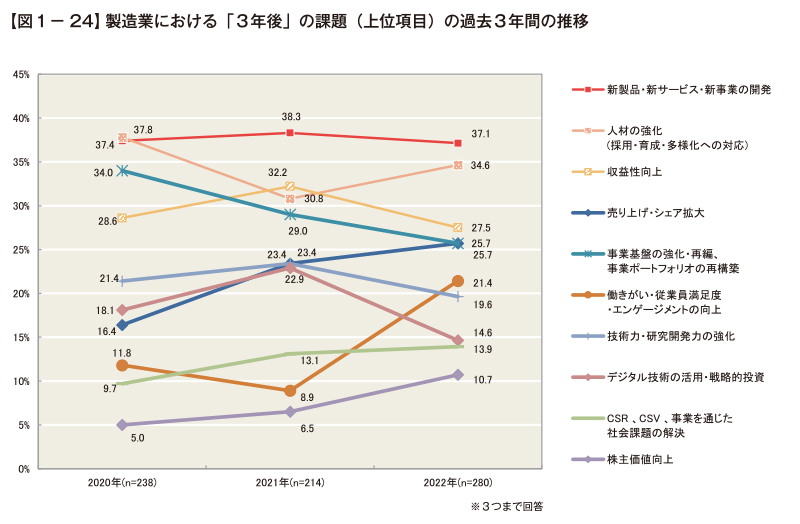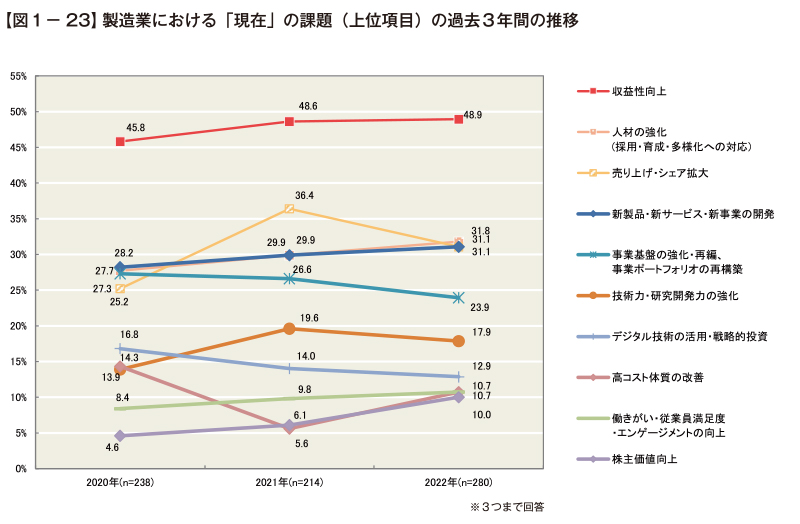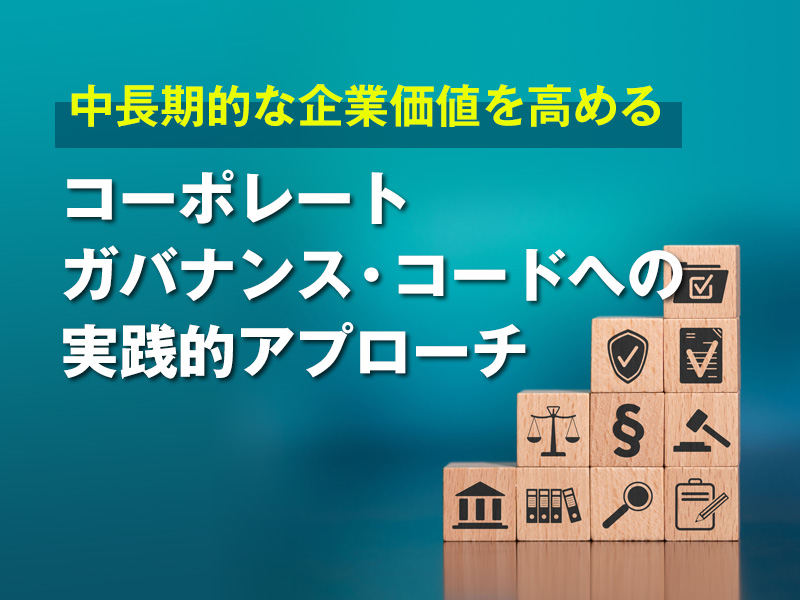
企業の信用醸成と価値評価において、重要な指標となるコーポレートガバナンス。2022年7月には、「CGSガイドライン」が改訂されました。社会の変化に適応するためにも、自社のコーポレートガバナンスを定期的に見直すことが求められます。
今回は、コーポレートガバナンス・コードの概要を示したうえで、経産省の「CGSガイドライン」をベースとした実践的なアプローチについて解説します。
重要度が高まるコーポレートガバナンス・コード
ご存じの通り、コーポレートガバナンス・コードは、東京証券取引所が定めたコーポレートガバナンスを実現するためのガイドラインです。制定は2015年3月、すべての上場企業に適用されたのは同年6月。2018年と2021年に改訂が行われ、現在に至っています。
コーポレートガバナンス・コードでは、コーポレートガバナンス(企業統治)について、「会社が、株主をはじめ顧客・ 従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」と定義しています。
コーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則として、「株主の権利・平等性の確保」「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」「適切な情報開示と透明性の確保」「取締役会等の責務」「株主との対話」があります。上場会社はもちろん、継続的成長や健全な経営をめざすすべての企業にとって、コーポレートガバナンス体制の構築は必要不可欠です。
(参考:株式会社東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnul.pdf)
「CGSガイドライン」改訂で求められる新たなガバナンス構築
コーポレートガバナンス・コードをふまえた上で、改革の実質化と深化を促しているのが、経営産業省が公表した「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」です。
CGSガイドラインは2017年3月に策定され、2022年7月に改訂が行われました。昨年の改訂では、日本企業全体の「稼ぐ力」の強化を図るため、中長期的な企業価値向上に必要となる経営陣や取締役会の役割、経営陣の指名・報酬の在り方など、ガバナンスの仕組み作りに必要な過程が示されています。
なお、CGSガイドラインは、企業が自主的な取り組みを行う上で参照するべき手引きのひとつであり、法的拘束力はありません。どのようなガバナンスを構築するかは、企業が置かれている状況や課題によって異なるので、まずは客観的に自社の現状を見極めるプロセスが重要となります。
ここからは、CGSガイドライン改訂における3つのポイントについて解説します。
(出典:経営産業省「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドラインhttps://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/cgs/guideline2022.pdf)
ポイント(1) 取締役会の強化
近年は、社外取締役を採用する企業が増加している背景もあり、取締役会の役割・機能を改めて見直すことが求められています。取締役会の大きな役割は、業務執行に対する「監督機能」と、経営に関わる重要事項を決定する「意思決定機能」の2つです。これまで、日本の企業では「意思決定機能」が重視されており、今後は「監督機能」に焦点をあてた改革を要求されます。
具体的には、取締役会で重要性が低いとされた案件の縮小や、経営戦略に関する議論の活発化などが挙げられます。今後は、社外取締役による経営責任の追及も、スタンダードになっていくはずです。
取締役会のガバナンス体制は、「(A)取締役会を監督に特化させることを志向する会社」と「(B)取締役会の意思決定機能を重視しつつ、取締役会内外の監督機能の強化を志向する会社」の2つに大別できます。どちらのモデルを選択するかは企業の戦略によるものの、モニタリング機能を重視した(A)のモデルに移行すれば、リスクテイクや客観性・透明性の向上が期待できます。
ポイント(2) 経営陣のリーダーシップ強化
「攻めのガバナンス」の実現には、企業の成長と価値向上の中心的な役割を担う社長・CEOといった経営陣の経営力強化が重要です。特に、グローバル展開を行う企業では、複雑な経営課題にも臆することなく取り組む強いリーダーシップの発揮が望まれます。
社会の変化に柔軟かつ迅速に対応し、執行機能を強化するためには、特定のテーマに応じた委員会の設置をすることもひとつの方法です。経営戦略、リスク管理、サスティナビリティなどのテーマで委員会を設立すれば、取締役会でも監督が行き届きやすく、執行側と監督側が相乗的に機能するきっかけとなりえるでしょう。
ポイント(3) 社内外の取締役・経営陣の選任と評価
コーポレートガバナンスでは、客観性のある視点や洞察を取り入れるため、社外取締役も活用が推奨されています。「(A)取締役会を監督に特化させることを志向する会社」の取締役会モデルを採用する場合、構成の過半数を社外取締役とすれば、客観的評価の精度を高められるはずです。
しかし実際には、社外取締役の認識不足など課題も多く、今後は一歩踏み込んで、社外取締役の資質向上や、活動のための環境整備に着手する必要があります。個々の社外取締役に適した研修やセミナーへの参加支援を積極的に行い、取締役会でもサポート体制の監督を行うなどの施策が有効です。
また、業務執行の意思決定スピードの向上とマネジメント強化のため、トップマネジメントチームに、ダイバーシティの観点を考慮した人材を採用するという手があります。社内外から候補を募り、持続的な人材育成計画を作成することで、公平性を保ちつつ経営人材を強化できます。
コーポレートガバナンス・コードが要請する経営層の育成が急務
コーポレートガバナンス・コードは、企業の持続的な成長と中長期的な価値向上のために、取締役・監査役として必要な知識の習得やアップデートを求めています。以下に原則4-14「取締役・監査役のトレーニング」を引用します。
「新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や更新等の研鑽に努めるべきである。このため、上場会社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うべきであり、取締役会は、こうした対応が適切に採られているか否かを確認すべきである。」
ここで重要なのは、全体的な経営力の強化のみならず、個々の現状に応じたトレーニングが必須とされていることです。社長・CEOの後継者や管理部門、各事業領域において適材を配したうえで、それぞれの知識や能力を適切に評価し、研修などを通じて必要な力を高めていかなければなりません。さらに、学習の成果について継続的にモニタリングし、外部に発信していく体制づくりも急ぐ必要があります。
健全かつ透明性の高い経営が要請される時代になり、経営者はガバナンスに関する本質的な理解と強いリーダーシップを求められています。いま一度、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を確認し、自社の体制における課題の洗い出しを行ったうえで、適切な打ち手について検討してみてはいかがでしょうか。