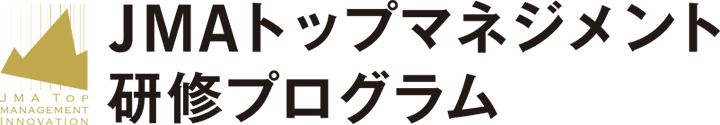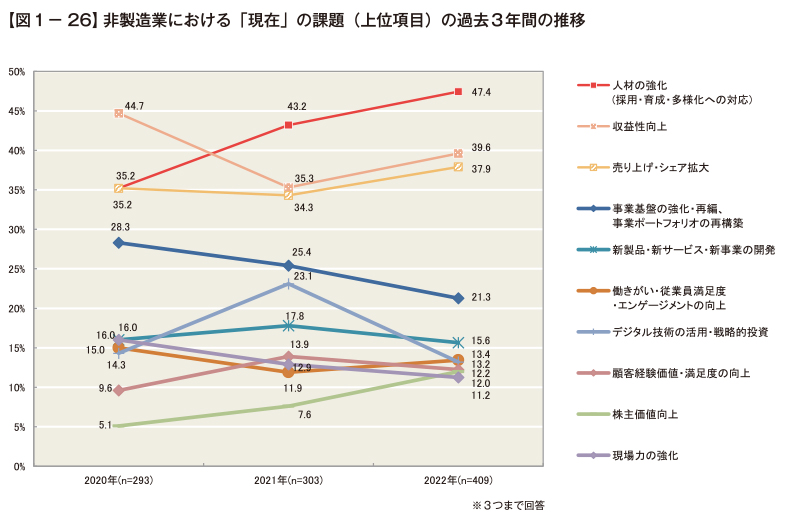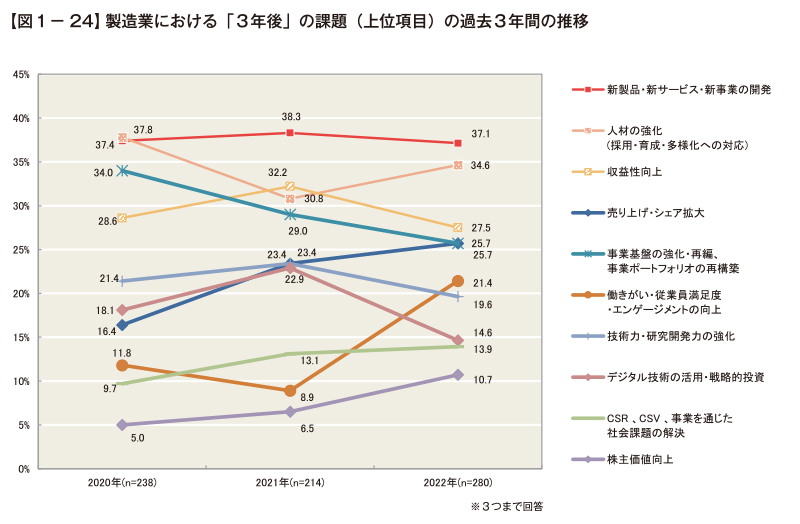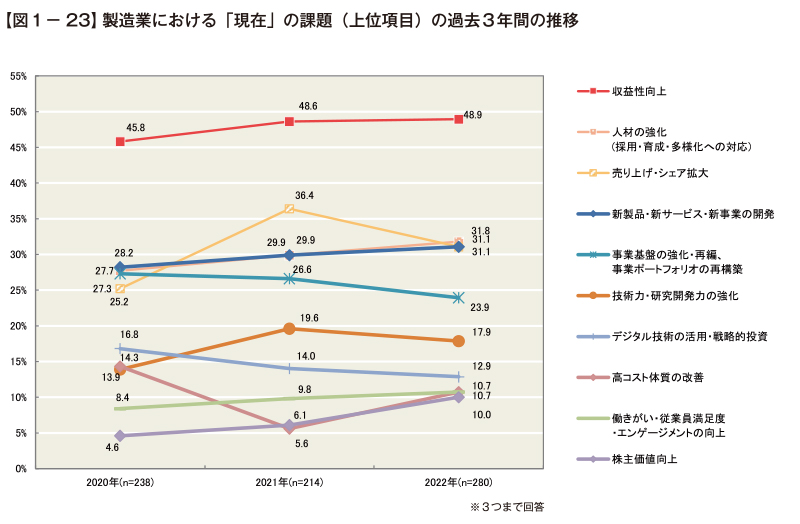日本能率協会の経営情報誌『JMAマネジメント』の誌面から「乱世の名将に学ぶ」全8回の連載をお届けしてまいります。
フリーライター 川田俊治 × JMAマネジメント編集室
明智光秀はなぜ本能寺宿泊中の信長を襲撃したのか。さまざまな説があるが、真相解明の糸口になりそうな、光秀直筆の手紙が発見された。岐阜県美濃加茂市民ミュージアム所蔵の書状で、三重大学の藤田達生教授の発表(2017年9月)によると、本能寺の変から10日後に書かれたというその手紙は、紀州雑賀衆で反信長派の頭目格・土橋重治に宛てた密書らしきもので、足利義昭を奉じての室町幕府再興の意図がうかがえる。
となると、光秀は天下人となるために謀叛を起こしたわけではなく、旧秩序への回帰を目論んで決起したことになる。
義昭の家来から両属を経て織田家直臣へ
明智光秀は、生まれ年や父の名など出自や青年期までの経歴については不明な点が多く、また終焉の地にも諸説ある。定説では、1526年(大永6)に土岐氏の支族・明智光綱の子として美濃国明智荘に生まれた。最期は、1582年(天正10)に山崎の戦いで大敗し、山科国小栗栖(現・京都市伏見区)で農民に刺殺された、とされる。明智氏は、美濃守護だった土岐氏の支流で、守護を押し退けて美濃の国主となった斎藤道三に仕えた一族だ。1556年(弘治2)、道三が息子の義龍と争って敗死したあと、明智氏は領地で籠城したが、義龍に攻められて一族離散となる。光秀はその後、越前国守護の朝倉義景に仕えた。
1565年(永禄8)、13代将軍・足利義輝が三好三人衆と松永久秀に弑逆される事件が起きた。身の危険を感じた義輝の弟・義昭は、将軍擁立と上洛を求めて有力武将のもとを行脚し、まず朝倉義景を頼った。そこから光秀に義昭との縁が生じる。
朝倉義景は義昭の要請に動こうとはしなかった。紆余曲折ののち、光秀が義昭の使者として訪ねたことで信長との縁も生じ、1568年(永禄11)の15代将軍義昭誕生へとつながる。
光秀は、義昭の家来であると同時に、信長の家臣という両属の立場で上洛軍団に加わり、その後、織田家直臣となったとされる。出自は問わず有能な人材を重用し、容赦なくこき使った信長のことだ。なし崩しで義昭との主従関係は消えざるをえなかったのだろう。それほど織田家における光秀の活躍は目覚ましかった。
豊臣政権確立後まで将軍位にあった足利義昭
信長と義昭との蜜月は長くつづかない。上洛の翌年10月に岐阜へ戻った信長は、年明けに義昭の権限を規制する通告をし、独自の立場で朝廷に昇殿して“天下静謐”の執行権を得た。 光秀は、上洛後の義昭の護衛を務め、三好三人衆の急襲を防いだりもしたが、やがて織田氏が支配する京都を中心とした五畿内の政務をつかさどる実質的な京都奉行職の一端を担う。さらに、金ヶ崎の戦いや比叡山焼き討ちなどで武功をあげ、1571年(元亀2)、信長から近江国滋賀郡約5万石を与えられ、坂本で築城にとりかかる。一方、義昭は本願寺や武田・朝倉などの反信長勢力を糾合して信長に戦いを挑んだが、その際、光秀は織田側で参戦している。
何度も挙兵に失敗した義昭は1573年(天正元)、拠りどころとする城を織田勢に次つぎに落とされ、ついにすべての官位を剥奪されて室町幕府崩壊……というのが定説だが、歴代朝廷の高官職員録にあたる『公卿補任』では義昭の将軍在位期間は1588年(天正16)までとなっている。
義昭は毛利家を頼って備後国鞆津に逃れ、幕府再興を図りつづける。これが信長の中国攻略の要因になった。
信長の死後、中国攻略を成し遂げて天下人となった豊臣秀吉は、九州平定に向かう途上、義昭の住まう備後の御所近くを訪ねて義昭と対面。将軍として島津氏に秀吉との和睦を勧めていた義昭は、重ねて島津氏に和睦の使者を送った。島津氏が秀吉に臣従を誓ったのち、義昭は京都に帰還し、関白であった秀吉とともに御所に参内して、1588年(天正16)2月に征夷大将軍を辞す。秀吉との間に、前々から何らかの密約があったと考えられる。
豊臣政権下で1万石を与えられ、秀吉の庇護を受けた義昭は1597年(慶長2)、波乱万丈の生涯を大坂で閉じた。享年61。自らの軍勢はもっていなかったが、信長より、そして光秀よりも長生きしたのだ。
教訓とするならば、たとえ名目上であれ、“権威”というものの世に及ぼす力はあなどれない(秀吉はそれをうまく活用して天下を引き寄せた)ことを覚えておきたい。
寄騎の細川父子、筒井順慶も味方せず秀吉に大敗
織田家において羽柴秀吉と並ぶ出頭人となった光秀は、伊勢貞興などの旧幕臣を多く召し抱え、完成した坂本城を本拠とした。1577年(天正5)から丹波攻略のほか紀州雑賀攻め、松永久秀が拠る信貴山城の戦いにも参加。翌年には中国攻略で苦戦する秀吉への援軍として播磨国へ出向き、荒木村重を攻める有岡城の戦いにも加わった。丹波平定が成ると信長から褒めたたえられ、丹波一国を加増されたばかりか、丹後の細川藤孝や大和の筒井順慶などの信長配下の大名が光秀の寄騎として配属された。それらの所領まで含めると、光秀の領地は約240万石にのぼったとか。1581年(天正9)には京都御馬揃の運営を任されるという栄誉も受け、光秀は自ら定めた家法のあとがきに「一族家臣は子孫に至るまで信長様への御奉公を忘れてはならない」と書いたという。
しかし、そんな順風満帆といってもいい状況が翌年、大きく変わる。5月、甲州征伐で功のあった徳川家康に対する饗応役を突如解かれ、秀吉の中国征伐への援軍を命じられたのだ。
天正10年6月1日、約1万3,000の光秀軍は丹波亀山城から出陣したが、向かったのは中国方面ではなく京都だった。「敵は本能寺にあり」——。雑兵は直前まで信長を襲うことを知らされていなかった。
あてにしていた寄騎で姻戚関係もあった細川藤孝・忠興父子は信長への弔意を表して光秀の誘いを拒絶。同じく寄騎の筒井順慶も結果的には秀吉に味方して、6月13日の山崎の戦いは大敗した。
大義名分に殉じながら汚名を着せられた光秀
2014年に亡くなった作家・山本兼一さんに『信長死すべし』という歴史巨編がある(角川書店)。本能寺の変直前までの帝、公卿・公家、家康など信長を取り巻く男たちの心理と言動から謎に迫り、「さもありなん」と多くの読者をうならせた作品だ。はたして帝の勅命があったのか、足利義昭の意が働いていたかどうかは闇のなかだが、甲州征伐後の信長から手のひらを返すような仕打ちを数かず受けたにせよ、明智光秀が個人的な怨恨で本能寺の変を起こしたとは考えにくい。
黒幕説が種々あり、信長を「目障りな男」と思う旧秩序の権力階級や、次なる天下人を狙う有力武将の名があがる。たしかに、信長が死んで得をしたのは、そういう男たちである。
光秀をその気にさせるだけの仕掛け、綿密なはかりごとが画策され、表舞台で行動した光秀に“逆賊”の汚名をかぶせ、黒幕たちは口をつぐむ。光秀は企てに乗せられ、ハシゴを外されたというしかない。「足利幕府再興」というのは、かつて義昭に仕えた光秀にとって、信長への忠誠心を捨てるに足る、魅力的な大義名分であっただろう。
こうした動きを考えるならば、クーデター的なはかりごとは、現代の組織でも大なり小なりあるが、表舞台に立つのは身を亡ぼすもとでもある。さらに、時代の変化を逆流させるような企ては、どんなに根回しをした計画でもついえやすい、とする教訓を得たい。
次回は「出自も明確でない徒手空拳の身から天下人へ昇りつめた豊臣秀吉」をお届けします。
本コラムは2017年11月の『JMAマネジメント』に掲載されたものです。
*年齢はいずれも数え年。歴史には諸説、諸解釈がありますことをあらかじめお断りしておきます。