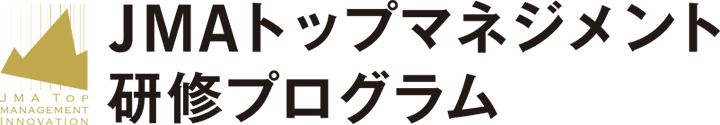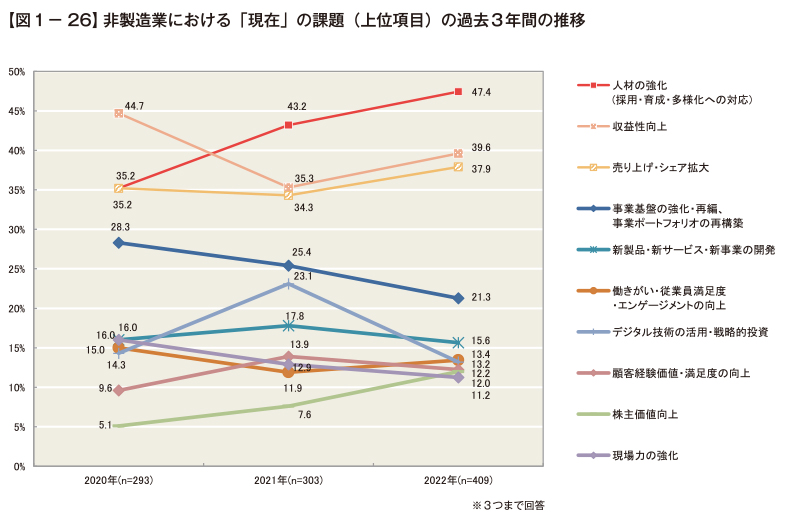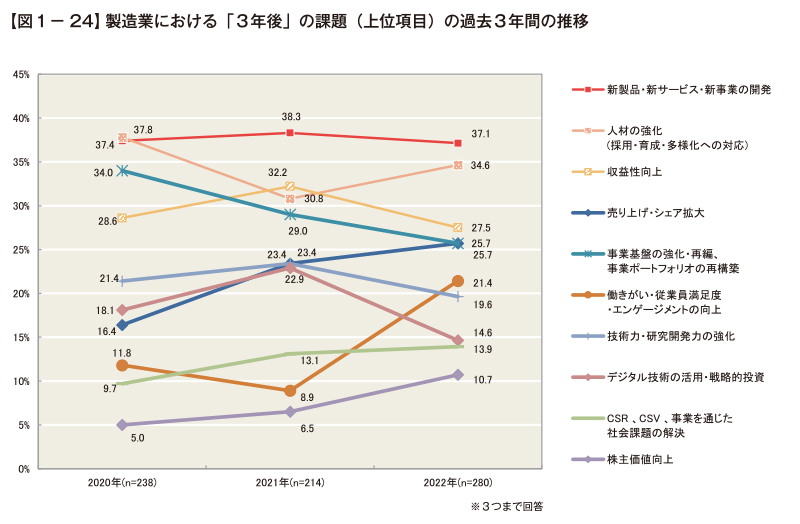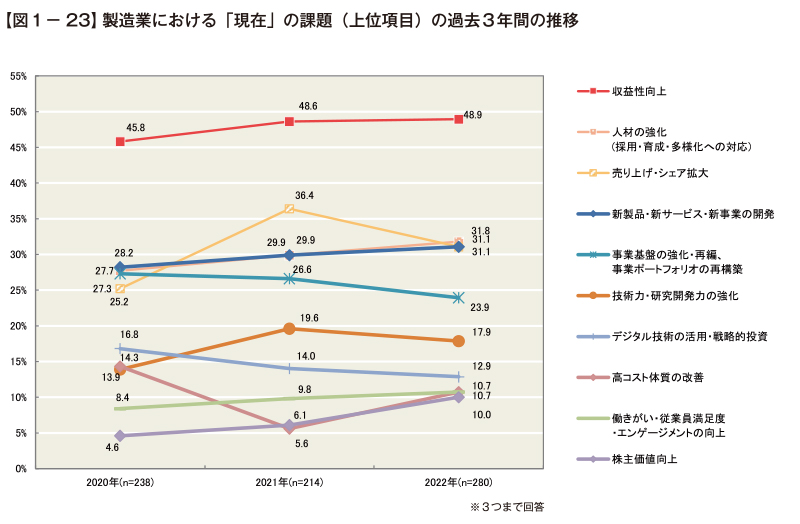2015年「プロフェッショナル・ビジネスリーダーコース」(PBL)を修了、そして2021年に「新任取締役セミナー」にご参加された大崎社長に、参加時のエピソードや気づき、修羅場体験やご自身の経営観について伺いました。
聞き手:曽根原幹人(日本能率協会・経営研究主幹)
初めての「他流試合」経験、経営全体を学ぶ機会に
PBLは非常に思い出深い。私が品質保証部長の時に会社派遣で参加した。社外の他流試合型研修に参加したのはPBLが初めてだった。それまで、自工会など同業の集まりでの議論はあったが、異業種の研修参加の経験はなかった。自分は技術畑で、経営には縁遠いと思っていたが、ケース企業の経営分析を行い、社長や役員と対話をしながら経営課題の解決策を考え、仮説を検証するという、課題形成~解決のアプローチを考えるという、いわゆる「経営のオペレーション」をこの時初めて知ることができた。
チーム研究・提案の結果について、自分の所属チームは惜しくも2位だった。悔しさが残ったが、自分たちとしてはケース企業の経営に必要な提案であり、一定の影響を与えることができたと、達成感を感じたことを覚えている。なお、「コストマネジメント」に関するチーム研究の提案内容は、研修後、自社の課題解決にも非常に役立った。
経営者としての“覚悟”を決めた取締役セミナー
2021年に取締役に就任した直後に参加したこのセミナーは、まさに「経営者としての覚悟を決める」3日間だったように思う。何よりも、経営者講話が印象深い。活躍する経営者の生の声を多数聴くことができた。自分が大切にしてきたことやこれまでの判断を検証したり、自分の考えを自問自答していくような事例が多数紹介された。まさに、生のケースステディをたくさん学んだ収穫の多い3日間であり、経営者としての責任や覚悟を強く認識したことを覚えている。欲を言えば、もっと侃々諤々の議論を参加者同士でたくさんしたかった。
2度の強烈な修羅場体験が今の自分を形成する
1つは、40歳前後のころ、会社を8年休職し労働組合の専従を務めたこと。書記長まで務め、労組のヒト・カネのマネジメント経験をした。その書記長時代、会社の業績が非常に悪く、700人の希望退職をせねばならなくなり、労組は組合員である従業員の雇用を守るのが仕事なのだが、それを受け入れざるを得ず大変辛い思いをした。当然組合員からは厳しい言葉を浴びせられ、また胸ぐらをつかまれるようなこともあった。自身の存在を否定された、強烈な経験だった。この経験から、「経営とは雇用を守ること、これは何かを考える際に雇用を天秤にかけてはいけない」と強く心に刻んだ。
もう一つの修羅場は、2017年秋の検査工程の不適切事案である。当時、私は品質保証本部長を務めており、事態の収束まで2年を要した。事業の急速な成長に、現場と品質が追い付いていなかったし、現場の出来事を経営は認識できていなかった。やはり製造業は「現場第一」(現場・現物・現実)であり、経営者は現場に降りていかねばならない、と肝に銘じ、これは社長になっても変わらないポリシーとしている。経営にインプットされてくる定量情報に加え、現場での対話から把握出来る定性情報を常に照らし合わせ、そこで生じる違和感が課題解決の糸口となる。
「現場第一主義」と「人財は全ての基本」が私の信条
持論を言うならば、やはり「現場第一主義」である。まさに“答えは現場にある”。そして「人財は全ての基本」、経営は人がすべてだ。この2つが私の経営の基軸である。
人財に関していえば、 “とんでもない人財、突拍子もない人財”ある種の“変態”な人財を大事にしていきたいと思っている。こういった人財こそが未来の価値の“種”(良い発想)を持っており、そして、そこに光を当て、育てていく人(土壌・風土)が当社の将来を創っていくと信じている。当社の歴史は、“危機と神風”の歴史である。経営が厳しいときに、キラッと光るテクノロジーが生まれ、経営を立て直すことができ、今に至っている。代表例が「アイサイト」である。こういったテクノロジーは“とんでもない人財”が手掛けてきた。そして、そこに光を当て、上手に技術開発や事業化を担う人もいた。こういった人財と組織風土を私は育んでいきたい。

リーダーはどんどん外に出て、
自己を客観視するチャンスを掴め
私は、幸いにも、会社のほとんど全ての機能を経験してきた。異動のチャンスがあれば、できるだけ手を挙げ、チャンスをつかむようにしてきた。決して経営者としての準備のためではなかったが、違うことをする好奇心・ワクワク感、そして達成感を感じることができた。その経験が今に生きている。これからのリーダー候補者には、是非チャンスを自ら掴みに行ってほしい。一つの仕事や部門に固執せず、多くの業務や機能を経験してほしい。加えて、社外に出て異業種の人たちと交流し見聞を広げる。そうすることで、自部門や当社の立ち位置、そして事業・経営の全体像が見えてくる。
また、経営感覚を養 うために子会社の社長を経験するとよいだろう。30代後半くらいに子会社に出向し経営を担い、全社視点を養うとともに修羅場を経験することで経営者としての資質が磨かれる。そこで活躍したら親会社に戻りさらに活躍するようなキャリアパスが有益だ。もちろん、大失敗しないよう親会社がフォローすることも大切である。
“社会・市場との対話”、
そして“組織・事業の柔軟性”が未来を創造する
「100年に一度の大変革期」と言われる自動車業界だが、大きな流れはカーボンニュートラル(CN)の達成である。その中核が自動車の電動化であり、当社もBEV(バッテリーEV車)の事業を10年以内にやり遂げると宣言し進めている。この道筋をしっかりつけていくのが私のミッションであると心得ている。加えて、日本の自動車産業が負けるわけにはいかない、という強い使命感を持って臨んでいる。
一方で、まだこの先社会や市場がどう変わっていくのか、見えにくいのも事実である。様々な方向性・手段を柔軟にラインナップし準備しつつ、社会・市場と対話としながら方向性を定めていく必要があろう。まさに、経営に高度な“柔軟性”が求められている。企業の規模が大きいほど、この柔軟性を持つことが難しいのだが、対話を通じて社員の不安を解消しつつ、ベクトルを合わせて組織の力を結集させていきたい。
経営者の決断の正しさは時代・歴史が決める
社長は孤独であるとつくづく感じる。いろんな意見が出るものの、最後は自分で決断しなければならない。社長の決断にはだれも反対はしないが、その決断の正しさは誰も教えてくれない。自分の判断・決断が正しかったのか否かは、時代が決め、歴史がそれを証明するのだろうと思う。過去に当時の社長が大型投資の意思決定を複数行い、それが原因でその後経営が大変苦しい時期があった。当時、意思決定した社長は、周囲から激しく非難をされていたが、実は、その大型投資で開発した技術や事業が、今の当社の経営を支えており、あの時の意思決定は正しかった、当社の今をつくったのだと評価されている。経営者の評価とはそのようなものだと心得ている。
以上