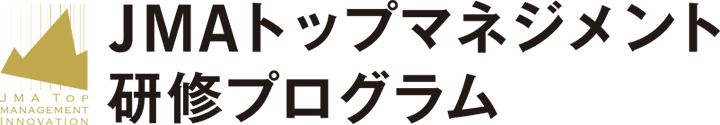味の素株式会社 特別顧問 山口範雄氏に、これから会社を担う役員の方々に対する動画メッセージや、ご自身が執行役員になられた当時の思い、経営者が常に磨くべき素養についてお伺いいたしました。
インタビュアー:一般社団法人日本能率協会 井上
特別メッセージ動画
~新任取締役・執行役員の方々へ
取締役に昇進したときの心境とは?
(井上)
山口さんが取締役になられたときの心境はどうだったのでしょうか。
何か新しい決意があったとか、過去とは違うとかいう意識を持ったなら、うかがいたいと思います。
何か新しい決意があったとか、過去とは違うとかいう意識を持ったなら、うかがいたいと思います。
(山口氏)
取締役になることと冷凍食品事業の分社の副社長になった時期が、ちょうど相前後していました。私個人からみて意味が大きかったのは、分社の副社長の方です。
私が出向いた先は、赤字事業を黒字化するために、本体から切り離されたのです。それだけに、必死になって働かなければなりませんでした。
取締役としてのいろいろな心づもりや、節目に当たってのものの考え方も、分社の黒字化という任務と完全に重なり合っていました。だから、意識の上では取締役というよりは、分社の実質トップだったのです。分社のトップは技術系の社長と事務系の副社長でした。
それで、対外的な交渉などはすべて私が取り仕切っていました。その結果、取締役以上に大きな覚悟をさせられましたね。
私が出向いた先は、赤字事業を黒字化するために、本体から切り離されたのです。それだけに、必死になって働かなければなりませんでした。
取締役としてのいろいろな心づもりや、節目に当たってのものの考え方も、分社の黒字化という任務と完全に重なり合っていました。だから、意識の上では取締役というよりは、分社の実質トップだったのです。分社のトップは技術系の社長と事務系の副社長でした。
それで、対外的な交渉などはすべて私が取り仕切っていました。その結果、取締役以上に大きな覚悟をさせられましたね。
分社でものの見方がどう変わったのか?
(井上)
赤字から収益を上げるという大きなミッションを背負わされたわけですね。
(山口氏)
そうなのです。そうすると、本体にいると分からないことがずいぶん、見えてきました。
例えば、間接費は本体だと調味料部門のような主力部門がより多く担ってくれています。そのような楽をしていてなおかつ赤字の部門が独立したわけです。関接費の削減にも腹をくくって取り組みしっかりスリムにしながら、機能面ではそれが進んだ方向にいかなければなりません。コストに対するものの見方も、シビアになりました。
それからうちはメーカーですから、ものを作るためのコスト、それにものを作るための設備投資、そしてものを売ることも、真剣に考える必要があります。
作って売るという基本機能を一生懸命にやっていたわけです。そうすると、その周辺に事業全体を成り立たせるため、いろいろな機能があることに気づきます。その典型が物流ですね。当時は物流機能をどう合理化するか、コストをどうやってギリギリに抑えるか、そういう視点は、作って売るという部分に比べ、非常に手薄でした。
うちの製品だと、調味料はドライ商品でしょう。水分を運んでいないから、物流費が安いのです。でも、冷凍食品はそうではありません。凍らせて冷たいまま運ぶわけですから、物流費が高くつきます。本体にいたころは、ドライ商品と同じ感覚で物流費を考えていましたが、分社で変わりました。そういうシビアな問題が分社で噴き出してきましたから。
そこが大きく変わった点です。
例えば、間接費は本体だと調味料部門のような主力部門がより多く担ってくれています。そのような楽をしていてなおかつ赤字の部門が独立したわけです。関接費の削減にも腹をくくって取り組みしっかりスリムにしながら、機能面ではそれが進んだ方向にいかなければなりません。コストに対するものの見方も、シビアになりました。
それからうちはメーカーですから、ものを作るためのコスト、それにものを作るための設備投資、そしてものを売ることも、真剣に考える必要があります。
作って売るという基本機能を一生懸命にやっていたわけです。そうすると、その周辺に事業全体を成り立たせるため、いろいろな機能があることに気づきます。その典型が物流ですね。当時は物流機能をどう合理化するか、コストをどうやってギリギリに抑えるか、そういう視点は、作って売るという部分に比べ、非常に手薄でした。
うちの製品だと、調味料はドライ商品でしょう。水分を運んでいないから、物流費が安いのです。でも、冷凍食品はそうではありません。凍らせて冷たいまま運ぶわけですから、物流費が高くつきます。本体にいたころは、ドライ商品と同じ感覚で物流費を考えていましたが、分社で変わりました。そういうシビアな問題が分社で噴き出してきましたから。
そこが大きく変わった点です。
事業部門と間接部門をどうつなぐのか?
(井上)
その後、本社に戻られ、それから社長に就任されました。そのときに取締役時代と違う考えは生まれましたか。特に行動面についてお聞かせください。
(山口氏)
本社に帰ったときは間接部門に戻りました。取り組んだ仕事は、おおむね分社の副社長になったときと同じです。私は長い間、事業部門にいました。直接事業に関わる仕事をした上に、分社も経験しました。それなのに、戻ったときは間接部門です。
多分、トップをやらせるには間接部門も経験しておくべきだと考えての人事だったのではないかと、今になったら推察します。でも、そのとき私はそんなことを思いもしませんでしたよ(笑)。それまでずっと事業部門から間接部門を見てきました。間接部門は事業部門に対する理解が薄いというのが、私の感想でした。だから、これを何とかしないといけないと思っていました。現場と本社機能に距離があると感じていたわけです。
それでその改善に必死に取り組みました。それが大事なことだと考えていました。
多分、トップをやらせるには間接部門も経験しておくべきだと考えての人事だったのではないかと、今になったら推察します。でも、そのとき私はそんなことを思いもしませんでしたよ(笑)。それまでずっと事業部門から間接部門を見てきました。間接部門は事業部門に対する理解が薄いというのが、私の感想でした。だから、これを何とかしないといけないと思っていました。現場と本社機能に距離があると感じていたわけです。
それでその改善に必死に取り組みました。それが大事なことだと考えていました。
(井上)
全社を見て間接部門と事業部門がきちんとつながるように配慮されていたわけですね。
(山口氏)
そうなのです。それは分社してみると、よく分かるのです。冷凍食品は薄利多売の典型です。やはり間接部門が高いと、赤字になってしまいます。作って売るという基本機能以外の部分にコスト削減の目が入っていないと、そうなってしまうのです。収益性の高いところなら、それが見えにくいものですけどね。
間接部門が赤字の原因になるわけですから、分社でやったのと同じことを本体でも実行すればいいと考えました。
間接部門が赤字の原因になるわけですから、分社でやったのと同じことを本体でも実行すればいいと考えました。
周辺事業や海外で人材が育つ2つの理由とは?
(井上)
今日の受講者の方々に間接部門の出身者はいませんでした。彼らはそういう経験をしてきてないかもしれませんが、目配りすることは当然、必要になってくるわけですね。
(山口氏)
そうです。うちも同じですけど、事業部門でいうと全社の利益を支えている主力部門と、そうでない部門があります。
主力部門がコケたら会社全体に響くので、周りが寄って集って助けます。ところが、どうでもいい部門は誰も助けてくれません。だから、全部自分たちでやらないといけないのです。
これは個人の育成という面で考えると、人材が非常に育ちます。
主力部門がコケたら会社全体に響くので、周りが寄って集って助けます。ところが、どうでもいい部門は誰も助けてくれません。だから、全部自分たちでやらないといけないのです。
これは個人の育成という面で考えると、人材が非常に育ちます。
(井上)
修羅場ですね。
(山口氏)
事業部門であったとしても、物流を自分で考えなければなりません。包材の安全性でも、主力部門なら調達部門の社員があれこれ世話をしてくれますが、冷凍食品では結局、自分たちでやるしかないのです。とにかく何から何まで自分たちでやるわけですから、これが人材の育成にとても良い効果があるわけです。
全く同じことが海外にもいえますね。海外へ行くと、そんなサポート部隊はありませんから。だから、人材が育つのはそういう周辺事業部門や海外を経験することなのです。そこを経験した人間は強いですよ。
全く同じことが海外にもいえますね。海外へ行くと、そんなサポート部隊はありませんから。だから、人材が育つのはそういう周辺事業部門や海外を経験することなのです。そこを経験した人間は強いですよ。
(井上)
それなら、王道でない部門の方に目を向けたらいいかもしれませんね。
(山口氏)
人材育成という観点でみれば、そうなりますね。
(井上)
彼らがもし自分で職場を選べるとしたら、ぜひそうしてほしいというメッセージになりそうです。
リーダーに必要な3つの要素とは?
(井上)
ご講演の中で「リーダーは全部できる必要がない。全部できたら神様じゃないか」という部分がありました。
多分、皆さんが聞いていてほっとしたところだと思いますが、これから先が見えないという情勢の中でリーダーに最も必要なものは何になるでしょうか。
多分、皆さんが聞いていてほっとしたところだと思いますが、これから先が見えないという情勢の中でリーダーに最も必要なものは何になるでしょうか。
(山口氏)
リーダーシップの源泉は3つあります。
① 企業理念にコミットすること
② 「あの人は仕事ができるね」といわれるような専門性を備えること
③ それといい人であること
この3つです。
特に専門性を備えた仕事ができることと、人間性が大事だと思います。専門性はその人の得意な部分をやればいいのです。別にどの部門がより重要などということはないと考えています。
① 企業理念にコミットすること
② 「あの人は仕事ができるね」といわれるような専門性を備えること
③ それといい人であること
この3つです。
特に専門性を備えた仕事ができることと、人間性が大事だと思います。専門性はその人の得意な部分をやればいいのです。別にどの部門がより重要などということはないと考えています。
(井上)
みんなから認められる専門性を持ち、人間性の面でも優れていれば、リーダーになれると考えているわけですね。
(山口氏)
でも、往々にして備わらないのです。専門性の高い人は、どうしても人間性が弱点になります。
仕事はできるけど嫌な奴だったり、いい人なのだけど頼りにならなかったりする人は、どこの会社にもいるでしょう。これは表裏の関係になっています。
専門性で優れた人は、人間性を培うことが非常に大切です。いい人はどこまでシャープな専門性を身に着けるかが課題になるでしょうね。
(井上)
専門性と人間性のバランスの話は、みなさんがこれから本当に苦労する部分ではないかと思います。
どうやってその両方を身に着けるのかが、大きな課題になっていくかもしれませんね。
どうやってその両方を身に着けるのかが、大きな課題になっていくかもしれませんね。
(山口氏)
ただ、ここまで来た人は基本的に両方備えていると思いますよ。そうじゃないと、取締役にはなりません。その前で脱落していますよ。
だから、取締役まで来た人は両方を基本的に備えていて、これからは経営職としての専門性、つまり全社視点を兼ね備えなくてはなりません。
これが結構、大変なことだと思いますよ。
今でも多くの会社でできていないのではないでしょうか。
取締役が部門代表の集まりになっているところが多いはずです。
だから、取締役まで来た人は両方を基本的に備えていて、これからは経営職としての専門性、つまり全社視点を兼ね備えなくてはなりません。
これが結構、大変なことだと思いますよ。
今でも多くの会社でできていないのではないでしょうか。
取締役が部門代表の集まりになっているところが多いはずです。
(井上)
今日のご講演時の質問をお聞きしていても、部門代表としての意識が抜けきっていない方が、多いのかもしれませんね。
経営理念の具現化に取締役が果たす役割とは?
(井上)
最後にその点も含め、これからそれぞれの会社を担っていく立場の方々に対し、山口さんから応援メッセージをいただきたいと思います。
(山口氏)
どこの会社も企業理念や経営理念を持っています。
それが下へ行くほど具現化され、毎日の仕事に生かされていることが非常に大事です。
たとえば、社長なり経営会議が作り上げた企業理念や経営理念をさらに一歩具現化して各組織に伝えるとしたら、その伝達役を担うのが取締役の最も大きな仕事の1つだといえるでしょう。
企業理念に即して組織が動けるのか、あるいは各組織の中に企業理念が浸透するかを左右するのは、旗振り役である取締役の働き一つです。
ぜひとも、皆さんがその役割をきっちり果たしてほしいと思っています。
それが下へ行くほど具現化され、毎日の仕事に生かされていることが非常に大事です。
たとえば、社長なり経営会議が作り上げた企業理念や経営理念をさらに一歩具現化して各組織に伝えるとしたら、その伝達役を担うのが取締役の最も大きな仕事の1つだといえるでしょう。
企業理念に即して組織が動けるのか、あるいは各組織の中に企業理念が浸透するかを左右するのは、旗振り役である取締役の働き一つです。
ぜひとも、皆さんがその役割をきっちり果たしてほしいと思っています。
(井上)
本日はどうもありがとうございました。