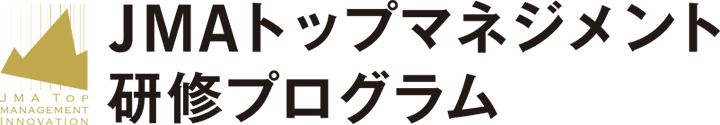ブラザー工業株式会社 代表取締役社長 小池様に、ご自身が役員になられた当時の思いや経営者として大切にしている力などについて、お話をお伺いいたしました。新任執行役員の方に向けての力強い動画メッセージもいただいておりますので、ぜひご覧ください。
インタビュアー:一般社団法人日本能率協会 井上
特別メッセージ動画
~新任取締役・執行役員の方々へ
役員になって変わった点とは?
(井上)
きょうの話の冒頭に、大所高所から見るということが出てきました。
小池社長が立場を変わられて、役員になった際、どんなことを心がけられましたか。
小池社長が立場を変わられて、役員になった際、どんなことを心がけられましたか。
(小池社長)
私自身、役員になったから変わった、ということは特にないかもしれません。
というのも、実は私はこの会社に入るときから、将来は社長になろうと考えていたんです。
というのも、実は私はこの会社に入るときから、将来は社長になろうと考えていたんです。
(井上)
今ではそんな人、少ないですよね。
(小池社長)
私が社長になり、引っ張っていかないとだめになると勝手に思っていたのです。
入社したときからそんな気持ちでいたわけですから、意識せずとも大所高所から見ていたのかもしれません。立場や役職など関係なしに自分の意見を主張していましたし、いろんなところに首を突っ込んでいました。
入社したときからそんな気持ちでいたわけですから、意識せずとも大所高所から見ていたのかもしれません。立場や役職など関係なしに自分の意見を主張していましたし、いろんなところに首を突っ込んでいました。
(井上)
今、日本能率協会では新入社員の調査をやっています。
将来は社長という人が少し増えたのですが、多分10%もいっていません。
将来は社長という人が少し増えたのですが、多分10%もいっていません。
(小池社長)
その10%の人たちも入社して5年も経てば、多くはめげるものです。
(井上)
30歳になったら、みんな現実が見えてきてほぼいなくなりますよね。
(小池社長)
ところが、入社3年目でアメリカへわたり新しいビジネスを始めることになり、それがうまくいったのです。そうしたら、本社から「しばらく日本に帰ってくるな。アメリカ人と骨を埋めよ」といわれました。それなら「仕方ないから、アメリカで天下を取るか」みたいな感じでいましたよ。すると、アメリカへわたって10年で、現地法人の取締役にしてもらいました。当時36歳で私が最年少でした。
(井上)
かなり早かったのですね。
(小池社長)
その7年後には社長になりました。本社の役職であればまだ部長クラスでしたが、本社の取締役であろうと部長であろうと、相手の立場など関係なく、言いたいことを言っていました。
(井上)
関係ないですよね。
(小池社長)
全く関係ありません。
失礼な物言いだけはなるべく避けていましたが、あまり耳触りのいいことはいっていなかったみたいです。
ブラジルが通貨危機に陥った時、本社から「ブラジルから撤退しろ」といわれたのですが、「嫌です」と答え、「お前、気が狂ったのか」と聞かれたら「いや、気は狂っていません」と返事していたようです。もちろん、簡単にあきらめるのが嫌で、何か打開策があるはずだとの考えのもとですが。
失礼な物言いだけはなるべく避けていましたが、あまり耳触りのいいことはいっていなかったみたいです。
ブラジルが通貨危機に陥った時、本社から「ブラジルから撤退しろ」といわれたのですが、「嫌です」と答え、「お前、気が狂ったのか」と聞かれたら「いや、気は狂っていません」と返事していたようです。もちろん、簡単にあきらめるのが嫌で、何か打開策があるはずだとの考えのもとですが。
圧倒的な当事者意識とは?
(井上)
社長が「こうしろ」といったとき、「冗談じゃねぇ」と反論してくる人が出てくるのが、1番いいわけですね。
(小池社長)
そうですね。それも、自分の担当分野に関わらず、です。
きょう来ている人たちは、みなさん執行役員であっても、製造担当、開発担当、総務担当という肩書きが付いていると思います。
例え総務担当の執行役員であったとしても、製造や営業、人事など他のいろいろな仕事に口を挟み、あれこれ意見をいうことが大事です。担当部署の偉い人という枠から、抜け出さなければいけません。
そういうことをためらいなくでき、どんどん口を挟めるかどうかが、重要になるでしょう。私はこれを圧倒的な当事者意識と呼んでいます。
さらに上の立場になると、周りからしょっちゅう口を挟まれ、けんかになることもあると思います。でも、けんかをしてでも、真正面からコミュニケーションすることも重要なことなのです。
きょう来ている人たちは、みなさん執行役員であっても、製造担当、開発担当、総務担当という肩書きが付いていると思います。
例え総務担当の執行役員であったとしても、製造や営業、人事など他のいろいろな仕事に口を挟み、あれこれ意見をいうことが大事です。担当部署の偉い人という枠から、抜け出さなければいけません。
そういうことをためらいなくでき、どんどん口を挟めるかどうかが、重要になるでしょう。私はこれを圧倒的な当事者意識と呼んでいます。
さらに上の立場になると、周りからしょっちゅう口を挟まれ、けんかになることもあると思います。でも、けんかをしてでも、真正面からコミュニケーションすることも重要なことなのです。
(井上)
今の部分はすごく重要なメッセージではないでしょうか。
私も執行役員の研修を何度もやってきましたが、会社の役員というよりも部門代表という意識を強く感じます。会社の役員と部門の責任者という立場を、切り分けできていないようにも見えました。
会社の代表として当事者意識を持たなければならないわけですね。
私も執行役員の研修を何度もやってきましたが、会社の役員というよりも部門代表という意識を強く感じます。会社の役員と部門の責任者という立場を、切り分けできていないようにも見えました。
会社の代表として当事者意識を持たなければならないわけですね。
(小池社長)
日本で執行役員というと、どうしても部長と取締役との間のポジションという感覚がありますが、そこに少し疑問を感じることがあります。
(井上)
中途半端だからですか。
(小池社長)
中途半端というよりは、株主に対して責任を負うのが取締役、会社の経営に責任を負うのが執行役員、という役割・権限の区別を明確にすべきだと思っています。
執行役員は会社経営の責任者なのですから、自分の担当分野という殻に閉じこもろうとせず、会社全体を俯瞰する気持ちで仕事をしなければいけません。
執行役員は会社経営の責任者なのですから、自分の担当分野という殻に閉じこもろうとせず、会社全体を俯瞰する気持ちで仕事をしなければいけません。
執行役員に求められる4つの視点とは?
(井上)
部門の視点ではなく、大所高所、会社全体の目線で仕事をしろということですね。
(小池社長)
「執行役員」という名前からすれば、それが当たり前でしょう、部長ではないのですから。
(井上)
その話はきょう、1番ほしかったところです。
執行役員は立場が曖昧なので、どうしても兼任の形で部門を持つ人が多いです。
執行役員兼生産本部長とか営業本部長とか。
どうしても「うちの部門は」という語り口になることが多いので、大所高所から会社全体の視点を持つことが必要になりますね。
執行役員は立場が曖昧なので、どうしても兼任の形で部門を持つ人が多いです。
執行役員兼生産本部長とか営業本部長とか。
どうしても「うちの部門は」という語り口になることが多いので、大所高所から会社全体の視点を持つことが必要になりますね。
(小池社長)
執行役員は会社を実際に経営する立場で、取締役はあくまで管理監督の役割を果たせばいいのです。
会社経営を実際に進めるのは、執行役員だということを、多くの日本人は取り違えています。
年配の方から「取締役を減らせば、取締役を目指す社員のモチベーションが落ちる」と文句をいわれることがあります。
私は「執行役員は会社の執行(経営)を司る責任者なのだ」と反論していますが、なかなか理解を得られないところがありますね。
会社経営を実際に進めるのは、執行役員だということを、多くの日本人は取り違えています。
年配の方から「取締役を減らせば、取締役を目指す社員のモチベーションが落ちる」と文句をいわれることがあります。
私は「執行役員は会社の執行(経営)を司る責任者なのだ」と反論していますが、なかなか理解を得られないところがありますね。
従業員とのブログコミュニケーションとは?
(井上)
話を聞いていて、従業員とのコミュニケーションがすごいと思いました。
(小池社長)
イントラネットでのブログの回数については、ギネスブックに載ってもいいぐらいだと自負していますよ。
(井上)
社長がそこに目をつけたきっかけはどこにありましたか。
(小池社長)
特に何もないのですが、何千人、何万人の従業員と直接、コミュニケーションを取るのは無理です。トップとしての公式なメッセージも真面目に発信していましたが、それだけだと不十分に思い、プライベートを含めて思いついたことをブログにまとめ、それをシェアしていったのです。
アメリカ時代にお客さんと話をするとき、面白い話題やユニークな話をしていました。それがコミュニケーションの秘訣だと感じていたからです。それで最初の2005年ごろは、週1回からスタートしました。
ブログは肩肘に力を入れてやっていたら、2カ月もすれば書かなくなる人が多いですよね。
「俺もそうなるのかな」と思っていましたが、全く逆で原稿のネタが溜まっていく一方だったのです。
そこで2007年ごろから週2回にしました。今は週2回書かなければいけないものだと思っています。
アメリカ時代にお客さんと話をするとき、面白い話題やユニークな話をしていました。それがコミュニケーションの秘訣だと感じていたからです。それで最初の2005年ごろは、週1回からスタートしました。
ブログは肩肘に力を入れてやっていたら、2カ月もすれば書かなくなる人が多いですよね。
「俺もそうなるのかな」と思っていましたが、全く逆で原稿のネタが溜まっていく一方だったのです。
そこで2007年ごろから週2回にしました。今は週2回書かなければいけないものだと思っています。
(井上)
すごいと思います。
きょうの受講者の中にも同じことにトライする人もいるでしょう。
成功するかどうかは分かりませんが。
きょうの受講者の中にも同じことにトライする人もいるでしょう。
成功するかどうかは分かりませんが。
(小池社長)
成功の秘訣は継続なのです。
私の場合は1回記事を公開すると、2,500か3,000ぐらいアクセスがあります。
それだけの人が見てくれていると思うと、やめられません。
それがモチベーションになっていますね。
私の場合は1回記事を公開すると、2,500か3,000ぐらいアクセスがあります。
それだけの人が見てくれていると思うと、やめられません。
それがモチベーションになっていますね。
執行役員が努力することとは?
(井上)
振り返って45歳から50歳ぐらいのとき、何か自己改善につながることをしていましたか。
(小池社長)
その当時はアメリカで英語の勉強をしていましたね。いろんな会社のトップの人と話すのに、あまりにもレベルの低い英語ではいけないと感じました。それでコミュニケーションを良くするために英語を学んだのです。
あとは興味があるセミナーには年中、出かけていましたよ。というのは、36歳でアメリカの現地法人の取締役になっているわけです。そのころから自分がこの会社を取り仕切ろうという責任感を抱いていました。取締役になる前はセールス関係の責任者でしたが、取締役になると他のことも知らないといけません。
サービスやロジスティクス、ITも知っておく必要が出てきます。
いろいろなことを考え始めると、あちこちのセミナーへ聞きに行き、勉強していたのです。隣の部署でどんなことをしているのか、興味を持ってみたり、いろんなところに首を突っ込んでいきました。
あとは興味があるセミナーには年中、出かけていましたよ。というのは、36歳でアメリカの現地法人の取締役になっているわけです。そのころから自分がこの会社を取り仕切ろうという責任感を抱いていました。取締役になる前はセールス関係の責任者でしたが、取締役になると他のことも知らないといけません。
サービスやロジスティクス、ITも知っておく必要が出てきます。
いろいろなことを考え始めると、あちこちのセミナーへ聞きに行き、勉強していたのです。隣の部署でどんなことをしているのか、興味を持ってみたり、いろんなところに首を突っ込んでいきました。
(井上)
執行役員の人たちもそれぞれ担当部署を持っているでしょうが、どんどん違う部門の話を聞いていけばいいわけですね。
(小池社長)
だからいってあげてください。
「あなたの会社にも執行役員会議があるでしょう。会議で他の部署の担当が説明することを黙って聞いていませんか。分かっていないから、質問さえできないのでしょう。」とね。
質問できないのは、分かっていないか、興味がないかのどちらかですよ。興味のない人は最悪ですね。
「あなたの会社にも執行役員会議があるでしょう。会議で他の部署の担当が説明することを黙って聞いていませんか。分かっていないから、質問さえできないのでしょう。」とね。
質問できないのは、分かっていないか、興味がないかのどちらかですよ。興味のない人は最悪ですね。
(井上)
そこで当事者意識があるかどうかが分かりますね。
(小池社長)
分かります。うちの会社でも、担当外の議題には全く興味を示さない人がいます。
(井上)
執行役員はそうはいかないですよね。
(小池社長)
本当はいけないのに、うちの会社でもそうなってしまいます。
技術系の役員は、セールスの話になると、興味を失ってしまいます。
技術系の役員は、セールスの話になると、興味を失ってしまいます。
(井上)
そういうケースは多いと思いますね。
(小池社長)
どの会社でも執行役員会議は必ず月に1、2回はあるはずです。
「そこで話している内容は自分で分かって聞いていますか。分からないときはしゃべった人にあとから内容を教えてもらっていますか」と聞いてみたらどうでしょう。
それってごく当たり前のPDCAの活動に入りますよ。
「そこで話している内容は自分で分かって聞いていますか。分からないときはしゃべった人にあとから内容を教えてもらっていますか」と聞いてみたらどうでしょう。
それってごく当たり前のPDCAの活動に入りますよ。
(井上)
実際にそれをやるのは難しいでしょうね。
(小池社長)
なぜ難しいのですか。
執行役員が話をし、分からなかったとき、私なら「分からないような説明をするな」といいますよ。
会議の場で聞くのは恥ずかしいという気持ちがあるのは分かりますが、それなら後で聞いて確認しないといけないでしょう。
執行役員が話をし、分からなかったとき、私なら「分からないような説明をするな」といいますよ。
会議の場で聞くのは恥ずかしいという気持ちがあるのは分かりますが、それなら後で聞いて確認しないといけないでしょう。
(井上)
自分の会社の話ですものね。
会社のあらゆるデータを頭に詰め込まなければならないのに、それをしないと入りませんよね。
会社のあらゆるデータを頭に詰め込まなければならないのに、それをしないと入りませんよね。
(小池社長)
ちゃんと理解することが必要です。
「苦手な財務や総務の話になると、昼寝しているのではないか」と聞いてやりなさい。
「苦手な財務や総務の話になると、昼寝しているのではないか」と聞いてやりなさい。
(井上)
よく耳にする「それは畑違いです」という言葉は立場上、ありえないわけですね。
(小池社長)
私の理論ではありえません。
経営者受難の時代にするべき3つのこととは?
(井上)
最後に受講生たちにメッセージをお願いします。
(小池社長)
セミナーに参加されたみなさん、お疲れさまでした。
冒頭に申し上げた通り、執行役員は会社を実際に経営する立場です。
これから会社を引っ張っていく、舵を切っていくのは、自分だと思い、生きがいを持って日々を過ごしてください。
自分に与えられた役割を果たすのは、当たり前です。でも、そこを乗り越え、自分の人格を磨くのは、その先に進むための重要な要素です。
そういう努力を決して怠らず、何もかも貪欲に吸収して前向きでいることを、忘れてはなりません。
それがあなたたちに社長への道を開くことになるのではないでしょうか。
ここまで来たら、あと5年頑張れば、そういう可能性が出てくるでしょう。
経営者にとって今の時代は世の中の変化が速すぎ、とても大変です。
経営者受難の時代であることは、覚悟しておく必要があります。
それでもビジネスマンとしてのゴールである会社のトップとして率先垂範し最後は気合いで乗り切るつもりで、努力してほしいと思います。
みなさんの活躍を大いに期待しています。
冒頭に申し上げた通り、執行役員は会社を実際に経営する立場です。
これから会社を引っ張っていく、舵を切っていくのは、自分だと思い、生きがいを持って日々を過ごしてください。
自分に与えられた役割を果たすのは、当たり前です。でも、そこを乗り越え、自分の人格を磨くのは、その先に進むための重要な要素です。
そういう努力を決して怠らず、何もかも貪欲に吸収して前向きでいることを、忘れてはなりません。
それがあなたたちに社長への道を開くことになるのではないでしょうか。
ここまで来たら、あと5年頑張れば、そういう可能性が出てくるでしょう。
経営者にとって今の時代は世の中の変化が速すぎ、とても大変です。
経営者受難の時代であることは、覚悟しておく必要があります。
それでもビジネスマンとしてのゴールである会社のトップとして率先垂範し最後は気合いで乗り切るつもりで、努力してほしいと思います。
みなさんの活躍を大いに期待しています。
(井上)
本当にどうもありがとうございました。