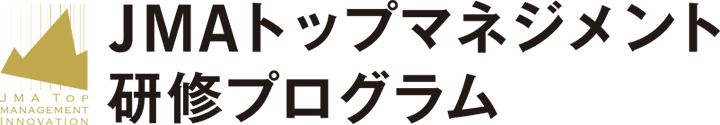カルビー株式会社 代表取締役社長 兼 COO 伊藤 秀二氏に、「自分からまずは変わることの大切さ」や「お客様との向き合い方」を伺いました。また「自己研鑽の大切さ」もお話いただきました。ぜひご覧ください。
自分が変わることによって相手が変わる?
改革を進める中で伝えたいメッセージとは?
経営者として必要な自己研鑽とは?
事業を通じて学ぶということは?
新任執行役員への応援メッセージは?
インタビュアー:一般社団法人日本能率協会 久保田
自分が変わることによって相手が変わる?
(JMA)
本日の新任執行役員セミナーには、30名ほどの受講者の方がいらしたのですが、聴講している姿や質疑応答から、講演席から感じられた感想をお聞かせいただけますか?
(伊藤氏)
皆さん問題意識をお持ちだと感じました。
「それをどう変えていこうか」という“思いみたいなもの”は、頷きながら話を聞いている様子からも見受けられましたし、私の講演について「そんなことをするんだ」ということも感じられていると思いました。
社長と執行役員で、異なる部分もあるかもしれませんが、どのような立場でも、こういう制度に変えるべきだとか、自分のスタンスがこれではいけないという考えがあると思います。
本日はあまり説明しませんでしたが、“マーケティング3.0”の時代に変わっていくという時に、私自身、まず自分から変わらなくてはいけないと考えています。
自分が変わることによって相手が変わる。
どうしても人間は相手を変えようとしてしまいがちですが、相手を変えることは難しい。
まずは自分を変えることによって、相手の言ってくることが変わり、相手の行動も変わってきます。
そのため、いわゆる業務転換“ビジネスを変えていこう”といった時に、変化を求めて社員に変われと言ったところで絶対に変わってはいかないと思うのです。やはり自分が先に変わることが必要だと考えています。
それは、別に会長や役員など、幹部に限らず、様々な立場の人たちが、とにかく“伊藤は変わろうとしている”ということを感じてもらえているならば、ありがたいなと思いますね。
「それをどう変えていこうか」という“思いみたいなもの”は、頷きながら話を聞いている様子からも見受けられましたし、私の講演について「そんなことをするんだ」ということも感じられていると思いました。
社長と執行役員で、異なる部分もあるかもしれませんが、どのような立場でも、こういう制度に変えるべきだとか、自分のスタンスがこれではいけないという考えがあると思います。
本日はあまり説明しませんでしたが、“マーケティング3.0”の時代に変わっていくという時に、私自身、まず自分から変わらなくてはいけないと考えています。
自分が変わることによって相手が変わる。
どうしても人間は相手を変えようとしてしまいがちですが、相手を変えることは難しい。
まずは自分を変えることによって、相手の言ってくることが変わり、相手の行動も変わってきます。
そのため、いわゆる業務転換“ビジネスを変えていこう”といった時に、変化を求めて社員に変われと言ったところで絶対に変わってはいかないと思うのです。やはり自分が先に変わることが必要だと考えています。
それは、別に会長や役員など、幹部に限らず、様々な立場の人たちが、とにかく“伊藤は変わろうとしている”ということを感じてもらえているならば、ありがたいなと思いますね。
(JMA)
受講者の皆様にも、そうした部分を感じて頂けたと思います。
改革を進める中で伝えたいメッセージとは?
(JMA)
伊藤様は、執行役員や取締役に就任され、立場が変わった、役割が変わったという時に、自分で意識をして変えた考え方や行動などはございますか。
(伊藤氏)
2001年に、東日本カンパニーの時に執行役員になりました。
現業のトップという立場で仕事をしていましたが、その次のステップへといった時に本社の消費者部門の担当になりました。
世の中では、大手企業による食品事件が起きていた時期でした。
食品メーカーとして、食品の安全・安心を前提にどのように商品を生産していくのかを考えると同時に、我々がお客様とどのようなお付き合いをしているのかを冷静に考えました。
その結果、お客様相談室に届くたくさんのご意見、お声を、とにかく全部聞いてみようというスタンスになりました。
今までは、お客様相談室に来たご指摘を、とりあえず大きな問題にしないように対応しよう、対処しようという雰囲気で終わっていたのですが、そうではなく、お客様は本質的に何かを伝えたいのであって、それに対応した時にお客様が納得するかどうかが大切なんだと思いましたね。
お客様が納得すれば、私どものブランドをより好きになってくれるということが経験上分かっていましたので、スタンスを全面的に変えて、お客様相談室を経由して、工場ですべての報告書を丁寧に分かりやすく作れるようにしました。
何がお客様の不満になったのか、どのように答えるとお客様は納得するのか、全部の工場で報告書を標準化して、全部やってもらうことにしたのです。
例えば商品の中に毛髪が入っていたら、お客様としては、「衛生管理が全然なっていない工場で作られているのではないか」と、不安に思ってしまう。
でも、工場にはエアシャワーがあって、手袋をして、マスクをしてという格好で、これだけのことをしてやっていますという報告書を作成して、そうした中でも混入してしまいましたと言えば、ほとんどのお客様は、「ここまでやっているのだったら問題ないわね」ということになって納得する。
ところが、例えばエアシャワーもないようなラインだと、「エアシャワーもついていないのか」となるわけです。
そして、お客様に報告するために改善を進めるのではなく、お客様は何が不満で、何に困っているのかということを常に追求していきました。
そしてやはり報告は早い方がいい。
1週間待たせたら、お客様は頭に来てしまう。
だから何日以内に報告をしましょう、直接伺いますと言いましょうというように、全部ルールとして決めました。
常に、お客様というのは、「不安だったり、不満な気持ち」になるものだということがベースとしてあったので、会社の改革をどんどん進めていくことによってお客様の不安、不満が減少し、企業に対する信頼度が上がっていくことにつながったと思います。
おいしいものを作って、広告宣伝を楽しくやれば売れるということではなくて、お客様と接して、何を考えて、どういうことをすればお客様は喜んでくれるのかという、この考え方と行動のサイクルを自分の中に入れることができました。
そうした経験を経てから、マーケティングを担当しているのですが、もしも先にマーケティングをやっていたら、そうはならなかったかもしれないですね。
一方で、ご指摘をいただいたお客様のところへ説明に行くという仕事が増えると困るという声が、営業マンから出てきました。
こうした活動を行っているうちに“全件対応に行ってください”と私が営業部内に指示したのですが、そんなことをしていたら、我々はお得意先に行けませんと営業は難色を示したのです。
でも、究極的に考えると、お得意先は消費者ですよね。
社員全員が、誰がなんのために仕事をしているのかということを、頭の中で整理しないといけない。
お客様に説明に行くことは、ある意味チャンスでもあり、重要な仕事であると認識を改めなくてはならない、こんな風に会社としての考え方を伝えていきました。
現業のトップという立場で仕事をしていましたが、その次のステップへといった時に本社の消費者部門の担当になりました。
世の中では、大手企業による食品事件が起きていた時期でした。
食品メーカーとして、食品の安全・安心を前提にどのように商品を生産していくのかを考えると同時に、我々がお客様とどのようなお付き合いをしているのかを冷静に考えました。
その結果、お客様相談室に届くたくさんのご意見、お声を、とにかく全部聞いてみようというスタンスになりました。
今までは、お客様相談室に来たご指摘を、とりあえず大きな問題にしないように対応しよう、対処しようという雰囲気で終わっていたのですが、そうではなく、お客様は本質的に何かを伝えたいのであって、それに対応した時にお客様が納得するかどうかが大切なんだと思いましたね。
お客様が納得すれば、私どものブランドをより好きになってくれるということが経験上分かっていましたので、スタンスを全面的に変えて、お客様相談室を経由して、工場ですべての報告書を丁寧に分かりやすく作れるようにしました。
何がお客様の不満になったのか、どのように答えるとお客様は納得するのか、全部の工場で報告書を標準化して、全部やってもらうことにしたのです。
例えば商品の中に毛髪が入っていたら、お客様としては、「衛生管理が全然なっていない工場で作られているのではないか」と、不安に思ってしまう。
でも、工場にはエアシャワーがあって、手袋をして、マスクをしてという格好で、これだけのことをしてやっていますという報告書を作成して、そうした中でも混入してしまいましたと言えば、ほとんどのお客様は、「ここまでやっているのだったら問題ないわね」ということになって納得する。
ところが、例えばエアシャワーもないようなラインだと、「エアシャワーもついていないのか」となるわけです。
そして、お客様に報告するために改善を進めるのではなく、お客様は何が不満で、何に困っているのかということを常に追求していきました。
そしてやはり報告は早い方がいい。
1週間待たせたら、お客様は頭に来てしまう。
だから何日以内に報告をしましょう、直接伺いますと言いましょうというように、全部ルールとして決めました。
常に、お客様というのは、「不安だったり、不満な気持ち」になるものだということがベースとしてあったので、会社の改革をどんどん進めていくことによってお客様の不安、不満が減少し、企業に対する信頼度が上がっていくことにつながったと思います。
おいしいものを作って、広告宣伝を楽しくやれば売れるということではなくて、お客様と接して、何を考えて、どういうことをすればお客様は喜んでくれるのかという、この考え方と行動のサイクルを自分の中に入れることができました。
そうした経験を経てから、マーケティングを担当しているのですが、もしも先にマーケティングをやっていたら、そうはならなかったかもしれないですね。
一方で、ご指摘をいただいたお客様のところへ説明に行くという仕事が増えると困るという声が、営業マンから出てきました。
こうした活動を行っているうちに“全件対応に行ってください”と私が営業部内に指示したのですが、そんなことをしていたら、我々はお得意先に行けませんと営業は難色を示したのです。
でも、究極的に考えると、お得意先は消費者ですよね。
社員全員が、誰がなんのために仕事をしているのかということを、頭の中で整理しないといけない。
お客様に説明に行くことは、ある意味チャンスでもあり、重要な仕事であると認識を改めなくてはならない、こんな風に会社としての考え方を伝えていきました。
(JMA)
それが常務の時に作られた、コーポレートブランドの「掘りだそう、自然の力。」というところに行き着くのかなと感じました。
(伊藤氏)
自然の力というのは、実は人間の力も含まれています。
人間も自分の能力を最大限に生かすということを含めて、メッセージとして伝えました。
人間も自分の能力を最大限に生かすということを含めて、メッセージとして伝えました。
経営者として必要な自己研鑽とは?
(JMA)
経営者として成果を出していくために、新任役員の方はどのような自己研鑽をしていくことが必要だと思われますか。
何か実践されていることや、おすすめの方法などをご紹介いただけますか?
何か実践されていることや、おすすめの方法などをご紹介いただけますか?
(伊藤氏)
私はもともと文系の出身で、それこそ営業、マーケティング、管理系といった仕事を経験していましたが、消費者部門で広報の仕事をしていた時に、世の中で化学物質に注目が集まり我々のつくりだす製品に“毒性があるのか”という問題に向き合わざるを得ない時期がありました。
栄養学や医学系の先生のところにずっと通い詰めて勉強し、じゃが芋についても農薬や種子の勉強をして、専門家の先生とも対等に話せるぐらいにまで全部吸収しました。
1年半ぐらいそういった研究をしていたときに、大学の先生から「伊藤さんは理系ですよね?」と言われるようになりました。
「私は文系だから無理」ではなくて、勉強すると分かるようになっていきますし、そうすることで抱えている問題に対して、解決する方法や必要なものが分かるようになります。
何か新しいことをしたいと思った時に、それを解決するためには、やはり学ぶことはとても重要だと思います。
会社の中だけでは、どうしても狭くなるというか、その中で得意な人にやってもらってしまうわけです。
外の人とどれだけ交流があって、外の人との合宿場みたいなところへ参加することは、とても大切だと思います。
そうしたことは、自分のネットワークだけでは難しいと思いますので、技術系の先生だったり、何らかの研究所の先生だったり、行政といったところへ行き、自分で勉強しなくてはいけないと思います。
世の中、知らないことばかりです。自社の商品について知っていることの上に、新しく勉強したことを重ねることによって、自分のフィールドが広くなったり、仕事のレベルが上ったりすると思います。
それを怠ってしまうと、結局は現状にとどまることになると思いますので、何かあったら、とにかく自分で関心を持ち、自分で解決できることが重要だと思います。
栄養学や医学系の先生のところにずっと通い詰めて勉強し、じゃが芋についても農薬や種子の勉強をして、専門家の先生とも対等に話せるぐらいにまで全部吸収しました。
1年半ぐらいそういった研究をしていたときに、大学の先生から「伊藤さんは理系ですよね?」と言われるようになりました。
「私は文系だから無理」ではなくて、勉強すると分かるようになっていきますし、そうすることで抱えている問題に対して、解決する方法や必要なものが分かるようになります。
何か新しいことをしたいと思った時に、それを解決するためには、やはり学ぶことはとても重要だと思います。
会社の中だけでは、どうしても狭くなるというか、その中で得意な人にやってもらってしまうわけです。
外の人とどれだけ交流があって、外の人との合宿場みたいなところへ参加することは、とても大切だと思います。
そうしたことは、自分のネットワークだけでは難しいと思いますので、技術系の先生だったり、何らかの研究所の先生だったり、行政といったところへ行き、自分で勉強しなくてはいけないと思います。
世の中、知らないことばかりです。自社の商品について知っていることの上に、新しく勉強したことを重ねることによって、自分のフィールドが広くなったり、仕事のレベルが上ったりすると思います。
それを怠ってしまうと、結局は現状にとどまることになると思いますので、何かあったら、とにかく自分で関心を持ち、自分で解決できることが重要だと思います。
事業を通じて学ぶということとは?
(JMA)
“人が成長して企業が成長している”というお話をされていたのが印象的ですが、業務を通じて自分の役割を全うするための学び、そして社外のネットワークも必要なのですね。
(伊藤氏)
社外に出ると、学ばなくてはという刺激も出てきますよね。
立場があがると、実務をやらなくても済んでしまう場面もあるかもしれませんが、対外的なところに行って話をする中で、知らないことが多ければ会話も満足にできませんね。
例えば、農業のことに詳しくなければ、全然話が進まない状況があるときに、誰か担当者を連れていくのかといったら、それはおかしな話だと思います。
そこはきちんと自分自身で、農業とはこういうことなのだということを勉強しなくてはいけない。
自分の考えを持つレベルまで勉強し、外のネットワークで自分の言葉で話をし、こういうことを考えているのですねと言われるまでなることが重要だと思います。
立場があがると、実務をやらなくても済んでしまう場面もあるかもしれませんが、対外的なところに行って話をする中で、知らないことが多ければ会話も満足にできませんね。
例えば、農業のことに詳しくなければ、全然話が進まない状況があるときに、誰か担当者を連れていくのかといったら、それはおかしな話だと思います。
そこはきちんと自分自身で、農業とはこういうことなのだということを勉強しなくてはいけない。
自分の考えを持つレベルまで勉強し、外のネットワークで自分の言葉で話をし、こういうことを考えているのですねと言われるまでなることが重要だと思います。
(JMA)
今日のセミナーでも、「馬鈴薯をたくさん作るのはどうして難しいのか」という質問があった時に、すぐに、農業政策のお話をされていましたね。
(伊藤氏)
それはもう私どもの生命線ですから、とにかく馬鈴薯には詳しくなくてはいけない。
私自身が農水省にも行きますし、農協さんにも行きますし、研究所にも行きますので、当然すぐに答えが出てくるわけであって、そこはもう社長としては避けて通れないと思っています。
私自身が農水省にも行きますし、農協さんにも行きますし、研究所にも行きますので、当然すぐに答えが出てくるわけであって、そこはもう社長としては避けて通れないと思っています。
新執行役員への応援メッセージは?
(JMA)
本日の講演では、1~2年先には、現業を課長や部長に任せて、執行役員はそれから先の長期スパンで仕事をするというお話をされていましたが、そうした仕事をするために留意すべき点、あるいは新任執行役員の方々への応援メッセージをお願いします。
(伊藤氏)
先ほども少し話をしましたが、長期的な仕事を中心にするというのは、いかに目の前の仕事を分権化できるかということになるわけですが、人に任せてやってもらうというのは意外とできません。
現業を後任者に任せ、もっと大きな視点で長期のことに取り組むことは、簡単そうに見えて実はとても難しいことです。
どうしても目の前にあることが入ってきて、全く無関心ではいられない。
その部分の解決は、もう彼に任せたのだから、彼女に任せたのだから、しっかりやってもらうことを信じ、自分は次の大きな仕事をしていこうという、心構えというのでしょうか。
常にそこを意識していないと、身近なところに自分を置いてしまいがちであることも現実としてあると思います。そこは留意する必要があります。
今も大事だけれども、次世代のことを考えて、何をすべきなのかということを自分の中心軸に置いて仕事ができるようになれば、本当にいいなと思います。
現業を後任者に任せ、もっと大きな視点で長期のことに取り組むことは、簡単そうに見えて実はとても難しいことです。
どうしても目の前にあることが入ってきて、全く無関心ではいられない。
その部分の解決は、もう彼に任せたのだから、彼女に任せたのだから、しっかりやってもらうことを信じ、自分は次の大きな仕事をしていこうという、心構えというのでしょうか。
常にそこを意識していないと、身近なところに自分を置いてしまいがちであることも現実としてあると思います。そこは留意する必要があります。
今も大事だけれども、次世代のことを考えて、何をすべきなのかということを自分の中心軸に置いて仕事ができるようになれば、本当にいいなと思います。
(JMA)
本日は本当にありがとうございました。
※伊藤氏には、第61回新任執行役員セミナー(2018年2月17日)でのご講演後、本インタビューにご協力いただきました。