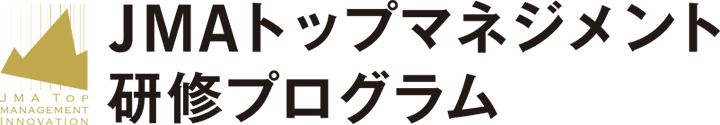アイロボット合同会社 代表執行役員社長 挽野 元氏に、「立場が上がると意識や行動はどのように変化するのか」「リーダーとして大事にすべきこと」等をご自身の経験に踏まえて伺いました。ぜひご覧ください。(※敬称略)
10年前の研修で学んだこととは?
立場が上がるたびにあった変化とは?
リーダーとして大事にしていることとは?
自分を知るために必要なこととは?
新任執行役員に対するメッセージは?
インタビュアー:一般社団法人日本能率協会 近田
10年前の研修で学んだこととは?
(JMA)
本日は、経営者講演でご登壇いただきましたが、10年ほど前、挽野様には受講者として「JTS新任執行役員セミナー」に参加いただきました。10年前のことも含め、本日の感想をお聞かせください。
(挽野)
コーディネータの佐藤先生には久々にお目にかかりました。佐藤さんがお話になったことはいろいろと覚えていますし、研修で学んだことも多々あります。
私が今日お話しした“浸透力”は、佐藤さんの教えに近いものです。私は佐藤さんの教えに従い、いろいろなことに取組みました。
同じことを何回も繰り返し伝える大切さ「自分が考えている以上に意識していないと、会社組織としての軸を作れない」とおっしゃっていましたが、この部分はとても印象深かったです。
佐藤さんから学んだことを自分の経験も踏まえて見直し、今日、新任執行役員セミナーを受講されている皆さんにお話しできた点は良かったと思います。
私が今日お話しした“浸透力”は、佐藤さんの教えに近いものです。私は佐藤さんの教えに従い、いろいろなことに取組みました。
同じことを何回も繰り返し伝える大切さ「自分が考えている以上に意識していないと、会社組織としての軸を作れない」とおっしゃっていましたが、この部分はとても印象深かったです。
佐藤さんから学んだことを自分の経験も踏まえて見直し、今日、新任執行役員セミナーを受講されている皆さんにお話しできた点は良かったと思います。
立場が上がるたびにあった変化とは?
(JMA)
挽野様は、最初にヒューレットパッカード(以下HP)で役員になられましたが、執行役員になったときに意識や行動は変わりましたか。
(挽野)
私の場合、役員になって事業体が変わりました。このセミナーを10年前に受講した後、自分の環境が一変し、全く違うところの事業責任者になったのです。新しい事業体の役員ですから、これはちゃんとやらねばと思うところがありました。緊張感がありましたね。諸先輩方がやってきた実績をどう生かすのか、会社にどう貢献できるのかをよく考えました。
(JMA)
実際に変わりましたか。
(挽野)
自分自身のスタイルを変えることはありませんでしたが、意思決定を含め自分の行動がすべて事業方針に反映されます。事業を始めたり、事業をやめたりなど、意思決定をする立場に立てる面白さと怖さの両面を感じていました。
(JMA)
その後取締役になるわけですが、取締役になったときは何か変化がありましたか。
(挽野)
取締役は執行だけでなく、他の事業への牽制なども役割に加わります。執行役員だと自分の事業の中で責任を持っていけばいいのですが、取締役は自分が所管しない他の事業に対する発言を求められます。きちんとやっていかなければ、善管注意義務を問われることもあります。これは重責だと感じました。
場合によっては株主やお客様から訴えられる可能性もあるわけですから、当然視野を広げなくてはいけません。他の事業から学び取ることも求められます。
場合によっては株主やお客様から訴えられる可能性もあるわけですから、当然視野を広げなくてはいけません。他の事業から学び取ることも求められます。
(JMA)
そこからボーズ株式会社に移られたわけですが、立場は社長でした。社長になって見える世界は違いますか。
(挽野)
それは孤独です。HPには20年も在籍していましたから、いろいろな人を知っていて、仲間も同僚もいました。ボーズは全く何も知らない会社でした。
そこでトップに立ち、何かをしようと意気込んでも、知っている人が周囲に誰もいません。社長という立場は基本的に孤独ですから、マネジメントしていくことが面白そうと思う一方で、この孤独とどう戦うかを考えなければなりませんでした。
そこでトップに立ち、何かをしようと意気込んでも、知っている人が周囲に誰もいません。社長という立場は基本的に孤独ですから、マネジメントしていくことが面白そうと思う一方で、この孤独とどう戦うかを考えなければなりませんでした。
(JMA)
孤独なときの支えは何でしょうか。
(挽野)
運動ですね。健康というのは大事です。健康を考えるようになったら、年を取ったことになるのかもしれませんが、やはり健康でなければ、しっかりと物事を考えることができないでしょう。健康だからちゃんと考え、ちゃんと動け、仕事もできるのです。そのために走っていましたよ。
あとは本を読むことですね。これは頭脳の健康を維持するためです。
あとは本を読むことですね。これは頭脳の健康を維持するためです。
(JMA)
どんなジャンルの本でしょうか。
(挽野)
小説、教養書、昔の哲学などです。いわゆる経営のハウツー本はあまり役に立ちません。人間はなぜ、こういうふうに行動するのかを考えさせてくれる本がいいですね。JMAの研修でもありましたが、リベラルアーツは大事だと思っていました。
(JMA)
孤独なときの自分の拠り所みたいな感じですか。
(挽野)
宗教論とか宗教観、歴史なんかがいいです。例えば、それぞれの宗教の生い立ちや考えを知ると、グローバルで働く上でとても役に立ちます。
リーダーとして大事にしていることとは?
(JMA)
先ほど孤独感と面白さという話が出ましたが、社長になって感じる執行役員や取締役と異なる面白さとはどんなことでしょう。
(挽野)
それは物事を決定することではないでしょうか。その結果が成功であっても失敗であっても、それはそれで醍醐味があります。上役として物事を決定できる仕事は、そんなに多くありません。その決めたことに対し、結果がついてくるわけです。
(JMA)
今、アイロボットジャパンの社長、リーダーとして意識されていることはありますか?
(挽野)
私はずっと外資系の会社でキャリアを積み重ねてきました。HPの創業者はヒューレットさんとパッカードさん、ボーズはドクターボーズ、アイロボットはコリン・アングルさんです。いずれも創業者の息吹みたいなものを感じられる会社にいたわけです。
今の会社は私が初めて、創業者とリアルタイムで話せる環境で、こんな素晴らしいことはないと思います。ボーズへ行ったときは、ドクターボーズがすぐに亡くなってしまいました。
ヒューレットさんとパッカードさんは現役でしたが、非常に大きな会社なので、話す機会があまりありませんでした。質問の答えになっているかどうか分かりませんが、創業者が考えていることに直に触れ、それに自分が共鳴、共感して仕事をするのは、ありがたいことです。
ヒューレットさんとパッカードさんは現役でしたが、非常に大きな会社なので、話す機会があまりありませんでした。質問の答えになっているかどうか分かりませんが、創業者が考えていることに直に触れ、それに自分が共鳴、共感して仕事をするのは、ありがたいことです。
(JMA)
働いている方々も自分が働く意義を大事にされていらっしゃるのでしょうか。
(挽野)
私は、多くのことをHPから学びました。ヒューレットさんとパッカードさんが企業設立後の最初の10年で作ったHPウェイは、企業がどうあるべきかをまとめたものです。
社会へどう貢献していくのか、社員にどうやって生き生きと働いてもらうのかなどが記されています。私にとっては、すべての原点となり、どの会社に移ってもその原点は生かしています。
社会へどう貢献していくのか、社員にどうやって生き生きと働いてもらうのかなどが記されています。私にとっては、すべての原点となり、どの会社に移ってもその原点は生かしています。
(JMA)
そうした原点を、どのように社員の皆さんに伝えているのでしょうか。
(挽野)
この半年は、現場の方がもっと生き生きと働き、会社に貢献してくれるようにするため、どうしたらいいのかずっと考えていました。先日、研修で販売員の方々を集め、冒頭で、先ほど申し上げた理念的な部分を私の方から伝えました。理念に共感してくれるお客さんもいることを、社員の誇りとしようという内容です。
今後は定期的にそういう場を設け、理念の浸透を図っていこうと考えています。
今後は定期的にそういう場を設け、理念の浸透を図っていこうと考えています。
自分を知るために必要なこととは?
(JMA)
物事をすべて上が決めるから現場の提案が上がってこないという話がありますが、解決は難しいようです。多くの会社や現場で、提案する組織に変えるためにどうするかで悩みを持っています。挽野様はどうお考えですか?
(挽野)
あまり怒ってはいけないのではないでしょうか。怒ると部下はビビってしまいます。地位のある者が怒ると、やはり怖いのでしょう。私もなるべく我慢して「なるほどね」というようにしています。その積み重ねが必要だと思います。
(JMA)
一昨日、三井住友ファイナンシャルグループの宮田孝一会長のごあいさつにも、「悪い情報を持ってこいといっているが、そのときに『じゃあ、どうするのか』といってはいけない」という話が出てきました。すごく面白いと思いました。
(挽野)
確かに、それをいうと、部下が話を持ってこなくなります。
(JMA)
だから、「よく来てくれた。いっしょに考えよう」といわないといけないそうです。
(挽野)
“よく報告してくれた”とほめるべきなのですが、ついつい「ふざけるな」とか怒ってしまいます。これは難しいですね。
(JMA)
役員や社長になってから、自己研鑽していることはありますか。
(挽野)
“異文化”を意識しています。そこから得た知見を仕事に生かしている部分は、結構ありますね。日本はモノカルチャーの国ですから、どうしても考え方が凝り固まりがちです。
イノベーションが生まれる素地は、国内だけとは限りませんから、中国や米国など他の国でなぜ、さまざまな動きが起きるのかを考えると、ヒントを得られることがあります。仕事柄、他の国の人、本社などと話す機会が多いのですが、今まで学んだことをさらに強化するため、他の国で起きていることに興味を持ち、よく聞くようにしています。
イノベーションが生まれる素地は、国内だけとは限りませんから、中国や米国など他の国でなぜ、さまざまな動きが起きるのかを考えると、ヒントを得られることがあります。仕事柄、他の国の人、本社などと話す機会が多いのですが、今まで学んだことをさらに強化するため、他の国で起きていることに興味を持ち、よく聞くようにしています。
(JMA)
先ほどのお話で自分を知ることが大事だとおっしゃっていましたが、自分を知るためにやっていることは何でしょうか?
(挽野)
家内や息子に聞くのです。家内だと頭に来るぐらい何でも話してくれます。会社にいて気がつかないことが分かります。体の動作はいろいろなメッセージを出しているものですが、姿勢が悪いとかいうことが家内の言葉から出てくるのです。
(JMA)
そういうフィードバックが沢山あるのでしょうか。
(挽野)
毎日ですよ。
新任執行役員に対するメッセージは?
(JMA)
最後に新任の執行役員の方にメッセージをお願いします。
(挽野)
執行役員のみなさん、このたびは御就任おめでとうございます。やはり、みなさんのエネルギー、健康は大事ですから、常に体と心の状態を高く保ち、情熱を持ってご活躍いただきたいと思います。頑張ってください。
本日はありがとうございました。
本日はありがとうございました。
※挽野氏には、第61回新任執行役員セミナー(2018年2月17日)でのご講演後、本インタビューにご協力いただきました。