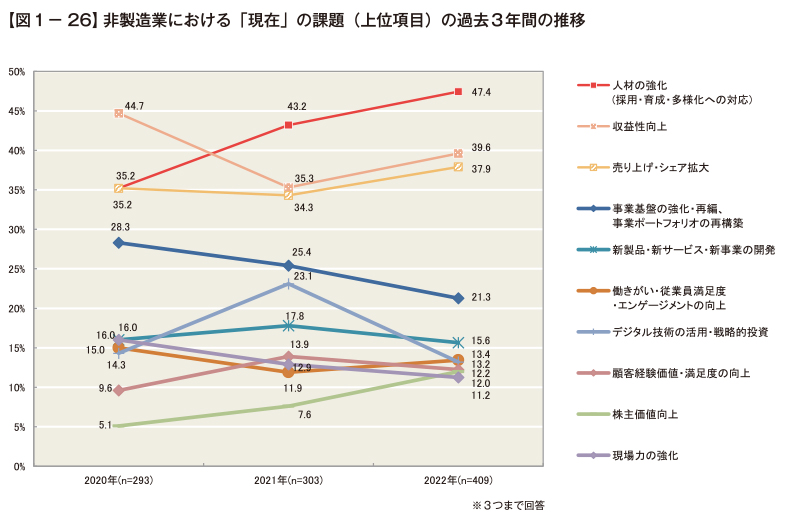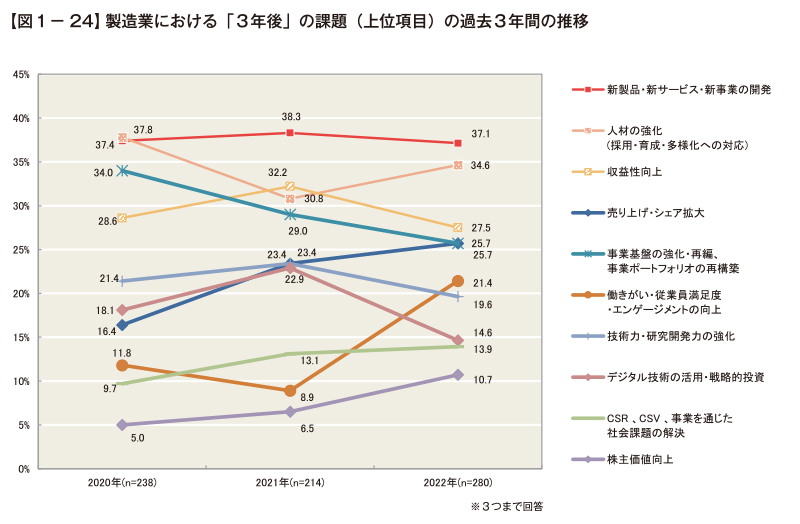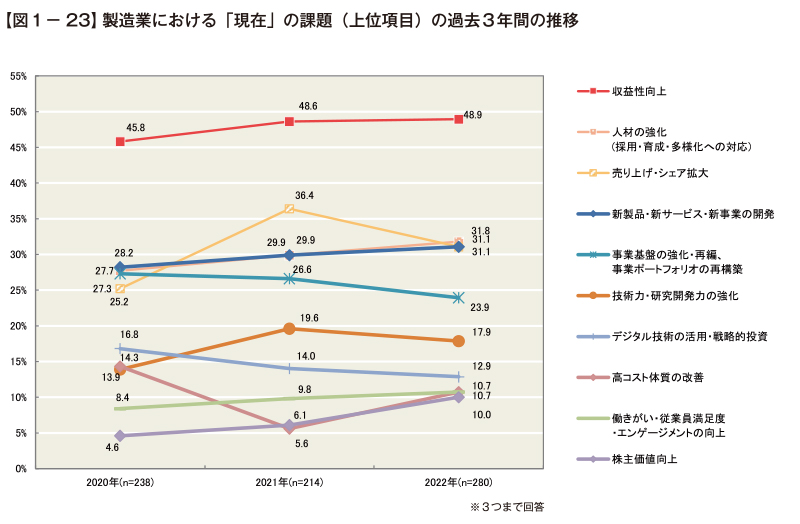日本能率協会の経営情報誌『JMAマネジメント』の誌面から「乱世の名将に学ぶ」全8回の連載をお届けしてまいります。
フリーライター 川田俊治 × JMAマネジメント編集室
毛利元就はきわめて筆まめな武将で、多数の手紙が残されている。そのため人物像はかなり明確で、行跡に不明な点も少ない。「三本の矢」の逸話のもととされる『三子教訓状』には、14カ条の教訓が記され、元就を“無類の説教魔”と評する研究家もいる。
集団指導体制で37歳にして安芸一国を支配
元就は、安芸国吉田郡山城(現・広島県安芸高田市吉田町)を本拠とする毛利弘元の次男として1497年(明応6)に生まれた。松寿丸と呼ばれた幼少期。その頃の毛利家は、国人領主、すなわち一地方豪族にすぎない。5歳にして母、10歳にして父が逝く。家督を継いで室町幕府の命で領地を離れ京都で役所勤めをしていた兄の興元も、1516年(永正13)に急死した。父、兄ともに死因は“酒毒”(飲酒による害毒)。酒が仇する血筋と自覚した元就は生涯“下戸”と称し、子孫にも酒は慎むべしと戒めている。
興元から留守中の領地差配を託された家臣の井上元盛は、松寿丸(元就)を邪魔者扱いした。元就は、住まいとしていた多治比猿掛城から追い出され、乞食呼ばわりされるほど惨めな少年時代を送った。
そんな苦難に耐え、興元が急死し、家督を継いだ嫡子・幸松丸の後見役に就き、知略を駆使しながら戦功を重ねることで毛利家の信望を集めていった。幸松丸が9歳で亡くなったことに伴い、元就が分家の身ながら毛利本家の家督を継いだのは1523年(大永3)。のちに毛利十八将に名を連ねる志道広良ら重臣に推され、晴れて吉田郡山城の主となった。
しかし、この家督相続に至る過程で、元就は安芸国にまで勢力を伸ばしてきていた尼子経久(出雲・隠岐守護代)と敵対するようになった。その一方で、有力守護大名の大内義隆とは関係を深め、後の1537年(天文6)には長男隆元を人質に出したほどである。 領内の国人領主らと敵対せずに共生を図る集団指導体制により、元就は安芸一国を支配下に治める。1533年(天文2)のことで、すでに37歳。まさに、遅咲きの苦労人といえよう。
事業承継の鏡となる『三矢の訓』
そこから領土を広げていく途上で見逃せないのが、次男元春と三男隆景の、近隣有力家への養子入りだ。元春が入った吉川家は、元就の妻の実家で、石見国で勢力を誇っていた。隆景が分家に入って本家を継ぐに至る小早川家は、備後国と瀬戸内海を地盤として水軍も抱えていた。いずれも実質は“お家乗っ取り”だが、これにより「毛利両川体制」が確立し、瀬戸内の強力水軍まで支配下に入れたことで元就の戦略は多彩になっていった。大きな節目は1551年(天文20)。大内家の家臣であった陶晴賢が謀反を起こしたことだ。その4年後、元就は一族を率い、厳島の戦いで奇襲によって陶晴賢が率いる大軍を破り、その2年後に長門・周防の2カ国を平定した。備後・備中・石見などへの進出も果たし、1566年(永禄9)には出雲の尼子義久を下す。さらに4年後、山中鹿之助などによる尼子再興軍を出雲・伯耆から一掃し、現在の中国地方5県を網羅する10カ国を支配する有力大名にのしあがった。
その間に元就は、家督を長男隆元に譲って隠居すると宣言していたが、少年時代に大内氏の本拠山口で人質として育ち公家文化になじんでいた隆元は、気弱なタイプだったか、政権委譲を固辞。実権はその後も元就がもちつづけていくことになるのだが、隠居宣言のおりに14カ条の遺訓を作成し、一族家中の結束を呼びかけた。
これが『三子教訓状』だ。実は、隆元は、父の元就より8年早く1563年(永禄6)に死去している。元就が死を前にした床で3人の息子に『三矢の訓の』を残したわけではないのは明白である。
現代社会でいえば、長男に本社社長の座を譲り会長に退いたが実権は保持し、次男と三男がトップを務めるグループ企業のアシストもあり、長期持続の礎を固めて現役のまま世を去った……といったところであろうか。
「兄弟3人の間に少しでも分けへだてがあってはならぬ。そんなことがあれば3人とも滅亡すると思え」と説く『三矢の訓』は、対等の関係で協力し合えという教えである。事業承継に際して候補者が複数いる場合のモデルケースとなろう。
国を簒奪する者、皆その家の大臣にて候
中国地方の周防・長門・安芸・石見・備後のほか豊前・筑前と九州の一部までの守護を兼ねていた大内義隆は、1542年(天文13)の出雲攻めで手痛い敗戦を喫して以降、戦に嫌気がさし、政務も放り出して“小京都”と呼ばれた山口で文化活動に没頭した。大内家の権限が陶晴賢の手に移ったことで治安が乱れることを憂えた元就は、大内義隆に「国を簒奪する者は、皆その家の大臣にて候」と諫言したという。
これは元就自身、当主の兄が不在中に辛い体験を強いられたことから得たものに相違ない。息子たちにも、たとえ重臣であろうとも、あまりに多くの権限を与えてはならないという主旨の手紙を書き送った。息子たちにはそのほか、「天下を競望するなかれ」ともいい残している。
元服前の少年期、家臣とともに厳島神社へ参拝に行ったおり、「松寿丸さまが安芸の主になられるように」と願ったという家臣を、「なぜ天下の主になれるようにと願わなかったのか」と叱った……そんな逸話がある。最初から安芸一国というような小さな目標を掲げていたのでは、それすら実現できずに終わる。理想は高くといっていた時期もあるようだが、年を重ねるにつれ、天下取りより「毛利の家名保全」を優先するようになっていく。
孫の代の毛利輝元(隆元の長男)は関ヶ原合戦で西軍総大将に担がれて大坂城入り。結局、合戦に参加せぬまま敗軍の将とされ、周防・長門2国37万石に減らされたが、毛利家は残り、長州藩は明治維新の立役者となった。元就の遺訓は無駄ではなかった。
言葉は心の使い
手紙を常時書きまくっただけあり、元就は“言葉”というものに対して独特の感性を備えていたようで、「言葉は心の使いである」との名言も遺している。その人の善悪、才能の有無、豪勇か臆病か、利口か愚かか、正直か否かなど一切が、その人の言葉でわかる、という確信を元就はもっていたようだ。たとえば、こういう話がある。明智光秀は織田信長に仕える前の浪人時代、妻を連れて仕官先を求めて西国を遍歴した。九州にまで足を伸ばしたがダメで、山口へ引き返したおり、浪人狩りにひっかかった。しかし、元就の寵臣のとりなしがあって元就に拝謁する機会を得た。弁舌さわやかに論じる光秀を、周囲がいくら褒めそやしても、元就は断固として召し抱えようとはしなかった。
一説では、光秀の頭骨の一部が、諸葛孔明により「謀叛の骨」と名づけられた骨相であることを看破したためというが、さわやかな弁舌の裏に隠れた光秀の心の奥底を見通したのかもしれない。
一方、元就と足利幕府との関係は良好であった。13代将軍義輝は体調を崩しがちな晩年の元就のもとに、名医として名高い曲直瀬道三門下の医者を派遣する気遣いを見せたとか。
さて、現代の史料研究者を辟易とさせるほど説教癖の強い元就だが、それはブレがないということであり、同じことを繰り返しいいつづけてこそ、組織の末端にまでトップの考えは浸透していく。リーダーたるもの、“無類の説教魔”とけなされようが、いうべきことはくどいほどいいつづける根気も必要だ。
次回は「「秀吉の九州征伐」「関ヶ原の戦い」二度の危機をくぐり抜けた島津義久」をお届けします。。
本コラムは2017年6月の『JMAマネジメント』に掲載されたものです。
*年齢はいずれも数え年。歴史には諸説、諸解釈がありますことをあらかじめお断りしておきます。