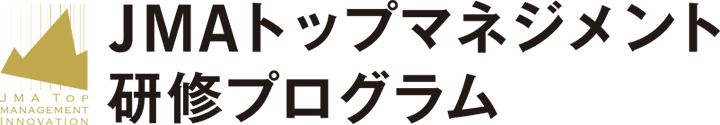東レ株式会社 代表取締役社長 日覺昭廣氏に、徹底した現場主義と経営者として高い倫理観に基づく、ゆるぎない経営者としての信念、ご持論を伺いました。ぜひご覧ください。(※敬称略)
・会社の本質的なものとは?
・なぜ言うことを聞かない子どもだったのか?
・全ての答えはどこにあるのか?
・イノベーションを成功させるためには?
・経営者に必要なリーダーシップとは?
・そこにある事実の重さとは?
インタビュアー:一般社団法人日本能率協会 井上
会社の本質的なものとは?
(JMA)
今日の執行役員セミナーに参加されたみなさんは、大役を担ったばかりですので、ご自身の責任感も含め、大先輩から聞きたいことがたくさんあると思います。
初めにまず、15年ぐらい前に少し時間を戻しまして、役員になられたのが2002年ですが、部門長から役員という役目を仰せつかったときに、何か心境の変化がありましたか。
(日覺)
僕はあまりなかったですね。
(JMA)
やっていることをそのまま続けようというスタンスでしたか。
(日覺)
そうですね。
みなさんのお話を聞くと、よく役員になったり社長になったりしたら、気持ちが変わると言われるのですけれど、僕は一切変りませんでした。
鈍感なのか、特に社長になったなら、非常にプレッシャーがあると言われるのですけど、僕は全然なかったですね。
鈍感なのか、特に社長になったなら、非常にプレッシャーがあると言われるのですけど、僕は全然なかったですね。
(JMA)
社長になられたのは7年前のことでしたね。
(日覺)
全然変化がないというのはおかしいけれど、僕は入社以来ずっとオーナーだったらどのように考えるのかということを基本的に考えてきたので、そのせいかもしれませんね。
その代わり上司とはよく衝突しましたけれど。
その代わり上司とはよく衝突しましたけれど。
(JMA)
入社されたときから、一般社員であっても、全体を俯瞰する目を持っていたということですか。
(日覺)
俯瞰する目とか、そんな難しいことではなく、僕はもともと兵庫県の三木出身で、中小企業が多い町だったから、中小企業のおやじさんたちが、1円のお金を稼ぐのも大変だと言ってみんな頑張っていたわけですよね。
だから、そういう気持ちで、本当に本質的なものは、会社としてどうなのかと思ってきたのです。
同期からは、お前は入社したときから偉そうなこと言っていた、社長みたいなこと言っていたと言われるのですけれど、別に社長だからと思った気持ちはなくて、本来会社としてこうあるべきじゃないのかと思っただけですよね。
ほとんどの人が変わると言うのですけれど、僕はそれをずっと貫いているから、社長になったからといって、急に何かが変わるわけでもありませんでした。
だから、そういう気持ちで、本当に本質的なものは、会社としてどうなのかと思ってきたのです。
同期からは、お前は入社したときから偉そうなこと言っていた、社長みたいなこと言っていたと言われるのですけれど、別に社長だからと思った気持ちはなくて、本来会社としてこうあるべきじゃないのかと思っただけですよね。
ほとんどの人が変わると言うのですけれど、僕はそれをずっと貫いているから、社長になったからといって、急に何かが変わるわけでもありませんでした。
(JMA)
では、現在のお考えを持たれたのは三木という場所なのですね。
(日覺)
ええ、三木は中小企業が多いですからね。
なぜ言うことを聞かない子どもだったのか?
(JMA)
三木という環境意外に、そういったお考えに至った要因は、学生時代のご経験などにはありませんか。
(日覺)
どうでしょう。
私は小学校時代から先生の言うこときかない子どもでしたからね。
先生が言っていることでも、時にはおかしいと思っていました。
通信簿ももらわないで帰ったりして、母親が代わりに通信簿もらいに行ったりしていましたよ。
要は、間違っていると思ったなら、言うこと聞かなかい子どもだったのです。
でも、普通のみんなは、先生の言うことを「はいはい」とか、勉強できる子は先生が言うことをよく聞いて、仲よくなるじゃないですか。
でも、僕は先生の言うことでもおかしいと思う時はありました。
だから、小さいときから変わっていたのです。
私は小学校時代から先生の言うこときかない子どもでしたからね。
先生が言っていることでも、時にはおかしいと思っていました。
通信簿ももらわないで帰ったりして、母親が代わりに通信簿もらいに行ったりしていましたよ。
要は、間違っていると思ったなら、言うこと聞かなかい子どもだったのです。
でも、普通のみんなは、先生の言うことを「はいはい」とか、勉強できる子は先生が言うことをよく聞いて、仲よくなるじゃないですか。
でも、僕は先生の言うことでもおかしいと思う時はありました。
だから、小さいときから変わっていたのです。
(JMA)
子どものころは先生と、会社に入ってからは上司とぶつかることがあったのですね。
(日覺)
そう、常にありましたね。
だって、今から思うと、結局、彼らはやはり自己保身と面子ですよね。
だって、今から思うと、結局、彼らはやはり自己保身と面子ですよね。
(JMA)
今日の講演にもありましたね。
(日覺)
だいたい課の面子とか、俺がこうやったのだからとか、そういうのが多いと思います。
そして逆鱗に触れるとか。
でも、そういう意味では、僕は正直に生きているだけですから。
講演でもお話ししました通り、東レに前田勝之助という名誉会長になった人がいたのですが、自分で事業を立て直したというすごい人なのです。
そして逆鱗に触れるとか。
でも、そういう意味では、僕は正直に生きているだけですから。
講演でもお話ししました通り、東レに前田勝之助という名誉会長になった人がいたのですが、自分で事業を立て直したというすごい人なのです。
(JMA)
海外の繊維事業を終わらせようというときに、前田さまが反対して立て直したのですよね。
(日覺)
その前田が社長だった時にアメリカに来られたときも、僕は少し言い合いになったことがあります。
それまで、そういう人はいなかったみたいです。
それまで、そういう人はいなかったみたいです。
全ての答えはどこにあるのか?
(JMA)
逆に、前田さまご自身は現場を見て、日覺社長が言っていることに、なるほどという部分があったということでしょうか。
(日覺)
そうでしょうね、多分。俺と同じこと考えているとよく言われましたから
前田名誉会長は、中学高校とすごく本を読んだらしく、文学部に行きたかったぐらい文学青年でしたが、たまたま彼の母親が、やはりこれから日本のために役立つのは化学だろうというので、化学科に行ったそうです。
前田名誉会長は、僕に「本を読んだだろう」と言うのです。
だから、考え方が一緒なのだと。
この本読んだか、あの本読んだかと言われましたが、僕は小さいときから本読むのが嫌いで、一切本を読んでいません。
前田名誉会長は、中学高校とすごく本を読んだらしく、文学部に行きたかったぐらい文学青年でしたが、たまたま彼の母親が、やはりこれから日本のために役立つのは化学だろうというので、化学科に行ったそうです。
前田名誉会長は、僕に「本を読んだだろう」と言うのです。
だから、考え方が一緒なのだと。
この本読んだか、あの本読んだかと言われましたが、僕は小さいときから本読むのが嫌いで、一切本を読んでいません。
(JMA)
少し意外な感じがします。
(日覺)
それで、なぜ考え方が同じなのかと思い、そのあとずっと考えていたら、結局は現場だったのです。
前田名誉会長がよく「現実直視」ということを常に言われていたのですが、僕は、「答えは全て現場にある」と思っていて、現場をよく見て考えたら同じ答えが出るのです
だから同じになったのだと、今ではそう思っています。
前田名誉会長がよく「現実直視」ということを常に言われていたのですが、僕は、「答えは全て現場にある」と思っていて、現場をよく見て考えたら同じ答えが出るのです
だから同じになったのだと、今ではそう思っています。
(JMA)
お2人の共通言語が現場だったのですね。
(日覺)
どの現場も1つしかなくて、事実がもうそこにあるのですから、事実を離れていろいろなことを世の中の人はよく言いますけれど、そんなことを言っていたら話が連想ゲームでおかしくなってしまいます。
けれど、現場を見たらもう事実しかなくて、事実からどうするかになり、出る答えが一緒になるのですよね。
僕自身も役員になって、経営会議とかに出ると、こんなに僕と同じこと考えている人いるのかと思いびっくりしました。
前田名誉会長が、お前は俺と同じこと考えていると言っていたのを、なぜかと考えると、前田名誉会長は、多分、誰の何という本とか読んで、それが僕の考えと同じだったから、ああいうこと言われたのですよね。
けれど、現場を見たらもう事実しかなくて、事実からどうするかになり、出る答えが一緒になるのですよね。
僕自身も役員になって、経営会議とかに出ると、こんなに僕と同じこと考えている人いるのかと思いびっくりしました。
前田名誉会長が、お前は俺と同じこと考えていると言っていたのを、なぜかと考えると、前田名誉会長は、多分、誰の何という本とか読んで、それが僕の考えと同じだったから、ああいうこと言われたのですよね。
ITがもたらす落とし穴とは?
(JMA)
現場から学んだことが、前田さまが本から学ばれたと同じことだったのですね。
(日覺)
ええ、だからそういうふうに勘違いされていただけで、前田名誉会長も現場を見て、現実直視ということを必死に言われていたたから、その考え方を自分が本を読んだからだと思われたのかもしれません。
でも、僕はそんな本の知識は一切ないし、いわゆる経営の本とかも読んだことがありません。
でも、僕はそんな本の知識は一切ないし、いわゆる経営の本とかも読んだことがありません。
(JMA)
前田さまと日覺社長が、現場が大事、現場で見ようというメッセージを発信し続けていることを考えると、発信をしなくなると、ともすれば会社の中で現場から離れた考えや、決断が発生する危険性も感じているのですか。
(日覺)
それは、最近のITの話ですよね。
ITは、まさに現場の状況を目に見えるかたちにするコンピューターセンサーがあり、コンピューターに全部の指示を入れるようになっているのですよね。
そうすると、何かトラブルがあるとコンピューターの画面を見ることになります。
そこで画面をパッと見て、本当は現場に行かないといけないのですがね。
だから僕はしきりに社内でも、やはり現場行って、ものを見て、現物と原理をしっかりと覚えないといけないと言っています。
コンピューターというのは、所詮は統計処理みたいなものです。
確かに、今のコンピューターは高性能になったから、いろいろな要因がある中で、すごく膨大なデータを入れて処理していくと、トラブルの原因がつかめるというツールとしては非常に優秀です。
けれど、それがあっても、現場を自分自身が理解してなければ、使いこなすことができないと思うのです。
だから、最近はプラントメンテナンスに注目しています。
PDCAをしっかり回すべきところを、パソコンでデータをチェックして、アクションするというような事になってはいけないと思っています。
ITは、まさに現場の状況を目に見えるかたちにするコンピューターセンサーがあり、コンピューターに全部の指示を入れるようになっているのですよね。
そうすると、何かトラブルがあるとコンピューターの画面を見ることになります。
そこで画面をパッと見て、本当は現場に行かないといけないのですがね。
だから僕はしきりに社内でも、やはり現場行って、ものを見て、現物と原理をしっかりと覚えないといけないと言っています。
コンピューターというのは、所詮は統計処理みたいなものです。
確かに、今のコンピューターは高性能になったから、いろいろな要因がある中で、すごく膨大なデータを入れて処理していくと、トラブルの原因がつかめるというツールとしては非常に優秀です。
けれど、それがあっても、現場を自分自身が理解してなければ、使いこなすことができないと思うのです。
だから、最近はプラントメンテナンスに注目しています。
PDCAをしっかり回すべきところを、パソコンでデータをチェックして、アクションするというような事になってはいけないと思っています。
(JMA)
それが表面的なところでなってしまって、現場が抜けてしまうのですよね。
今のデジタルの流れだからこそ現場が重要になりますよね。
今のデジタルの流れだからこそ現場が重要になりますよね。
(日覺)
少なくても僕はみんなにそう言っています。
現場は大切で、特にデータが全部出てくるようになって、センサーで全てが見えるようになると、余計に何か机上で全部を終わらせてしまおうとするので、もう1回現場の教育をやり直して、本質的なところをつかませないとだめです。
だから、最近の傾向としてトラブルが大きくなってしまうのです。
現場は大切で、特にデータが全部出てくるようになって、センサーで全てが見えるようになると、余計に何か机上で全部を終わらせてしまおうとするので、もう1回現場の教育をやり直して、本質的なところをつかませないとだめです。
だから、最近の傾向としてトラブルが大きくなってしまうのです。
なぜ大きなトラブルが出るのか?
(JMA)
数字で見ると、ほんの少しの兆候かもしれません。
(日覺)
トラブルの件数は減るのだけれど、1つのトラブルの規模が大きくなってしまいます。
特に対応が遅くなる傾向があります。
確かに、昔はちょこちょこあった小さなトラブルの件数は減るのです。
しかし、件数は減っても、何でこれがこんな大きなトラブルになるのかというくらい1件がボンと出てしまいます。
それだけ現場力が落ちてきているのですね。
だから、そこを徹底的にやり直すつもりです。
特に対応が遅くなる傾向があります。
確かに、昔はちょこちょこあった小さなトラブルの件数は減るのです。
しかし、件数は減っても、何でこれがこんな大きなトラブルになるのかというくらい1件がボンと出てしまいます。
それだけ現場力が落ちてきているのですね。
だから、そこを徹底的にやり直すつもりです。
(JMA)
これからの役員の方が難しいのは、パソコンで見た統計データなど、あたかも現場がわかったような気にさせるツールが増えているという点です。
今日、講演に来られた役員の方にも、数字でわかったふりはせずに、現場に行くということが伝わったかもしれませんね。
今日、講演に来られた役員の方にも、数字でわかったふりはせずに、現場に行くということが伝わったかもしれませんね。
(日覺)
やはり現場を見ないとダメで、全ては現場にあり、営業も、研究も、生産もそうです。
普通は現場というと、生産現場だけしか思い浮かばないのですが、営業なんて本当に現場で相手と経験しないと、本気度など、本当はどう思っているのかは顔色を見ないとわかりません。
普通は現場というと、生産現場だけしか思い浮かばないのですが、営業なんて本当に現場で相手と経験しないと、本気度など、本当はどう思っているのかは顔色を見ないとわかりません。
(JMA)
そうですね。
今日の日覺社長のご講演の中で本当に面白かったのが、勤務時間の20%を自由な研究に充てられる「アングラ研究」のところでした。創業時から研究者の自由な研究を奨励されているそうですね。
今日の日覺社長のご講演の中で本当に面白かったのが、勤務時間の20%を自由な研究に充てられる「アングラ研究」のところでした。創業時から研究者の自由な研究を奨励されているそうですね。
(日覺)
研究者もみんな自分なりの考えがありますから、上司から言われるか、課で方向を決めても、やはりこっちのほうがいいのではないかとか思うことがあると思うのです。
それをガチガチに規制してしまって、俺の言った通りにやれと言ってしまうのではなく、確かに今の時点ではみんながこっちのほうがいいと思っているけれど、こういうやり方もあるから自分はこっちでやってみたいとかはいいのです。
もちろんフィルムの研究をやっているのに、医薬の研究がおもろくなったとか、そんなことはダメですよね。
それをガチガチに規制してしまって、俺の言った通りにやれと言ってしまうのではなく、確かに今の時点ではみんながこっちのほうがいいと思っているけれど、こういうやり方もあるから自分はこっちでやってみたいとかはいいのです。
もちろんフィルムの研究をやっているのに、医薬の研究がおもろくなったとか、そんなことはダメですよね。
イノベーションを成功させるためには?
(JMA)
少し関連する話では、どこの会社でも、最近、話題にあがっているイノベーションですが、御社では、ボーイングさんとか、ユニクロさんなどの他社と組んだイノベーションがあると思います。
イノベーションのための方法として、今後もパートナーとの連携やオープンイノベーションという位置づけはもっと強くなると理解してよろしいですか。
イノベーションのための方法として、今後もパートナーとの連携やオープンイノベーションという位置づけはもっと強くなると理解してよろしいですか。
(日覺)
1つの要素技術で解決できる問題は、だんだん少なくなってきますから、そういった意味で、かなりオープンに、それにお客さんと一体になってやっていかないと解決できませんよね。
両方から歩み寄ることも必要でしょう。
外国でも基本的に一緒ですよね。
両方から歩み寄ることも必要でしょう。
外国でも基本的に一緒ですよね。
担当領域のトップがすべきこととは?
(JMA)
新しい取り組みというのは、本当にかなり苦労されているという話を聞いていますので、多分、御社のいろいろな他社との取り組みは、とても参考になるのではと思っています。
最後に、今日のご講演で、人材育成の重要性も説いていらっしゃいましたが、現場の重要性なども加えながら、役員という立場に対し、社長から見て求めたいものは、あるべき論を含めてどういうものが1番なのでしょうか。
最後に、今日のご講演で、人材育成の重要性も説いていらっしゃいましたが、現場の重要性なども加えながら、役員という立場に対し、社長から見て求めたいものは、あるべき論を含めてどういうものが1番なのでしょうか。
(日覺)
役員というのは、その担当領域のリーダーで、その領域のトップですよね。
だから、しっかりと方向を間違わないようにしないといけません。
僕は間違った方向に部下やお金を使うのは背任行為だと言っているのです。
泣いて馬謖(ばしょく)を斬るではありませんが、やはりリーダーが間違ったなら、戦争に負けるわけで、完全に負けというのはダメなのです。
そのためにはしっかりと現場と現状の把握をした上で、どうすべきかを決めないと、時流に迎合したり、人が言われたことだけをしたりしていてはダメです。
担当領域のトップなのですから、自分で信念を持って確信できることを、信念を持ってやり通さないといけません。
特に東レの場合は全部門に取締役という担当役員がいて、今のアメリカ型と違い代表がちゃんと取締役会に出て、意見を言える仕組みにしていますからね。
だから、しっかりと方向を間違わないようにしないといけません。
僕は間違った方向に部下やお金を使うのは背任行為だと言っているのです。
泣いて馬謖(ばしょく)を斬るではありませんが、やはりリーダーが間違ったなら、戦争に負けるわけで、完全に負けというのはダメなのです。
そのためにはしっかりと現場と現状の把握をした上で、どうすべきかを決めないと、時流に迎合したり、人が言われたことだけをしたりしていてはダメです。
担当領域のトップなのですから、自分で信念を持って確信できることを、信念を持ってやり通さないといけません。
特に東レの場合は全部門に取締役という担当役員がいて、今のアメリカ型と違い代表がちゃんと取締役会に出て、意見を言える仕組みにしていますからね。
(JMA)
手前どもでガバナンスの研究会を開いているのですけれど、実は真っ先に話あったのはその点で、いち早く取り入れた会社が、粉飾も含めたかたちを防げませんでした。
(日覺)
やはり社外取締役が見える限界はありますよね。
その会社の知識においてハンディを抱えている社外取締役にチェック機能をもたせることは無理があると思います。
その会社の知識においてハンディを抱えている社外取締役にチェック機能をもたせることは無理があると思います。
(JMA)
まさにその通りだった調査報告があります。
(日覺)
社外取締役がブレーキかけるというけれど、当事者でない人は中身わかりません。
わからない人が監督するのがいいというのは、自己矛盾だと思いますね。
やはり責任ある立場の当事者が倫理観を持ってやるしかないです。
わからない人が監督するのがいいというのは、自己矛盾だと思いますね。
やはり責任ある立場の当事者が倫理観を持ってやるしかないです。
なぜアメリカに追従してはならないのか?
(JMA)
わかった人間が社内にいるはずだから、あとはその人間が倫理観を持ってやれば、正しくないことはできるわけがありませんよね。
(日覺)
そうなのです。手っ取り早いので、アメリカの真似をしているだけです。
しかし、一方のアメリカはもう変わってきています。
日本的経営みたいなことが、アメリカでもイギリスでも叫ばれてきているのです。
こんなときに日本がまだ以前のアメリカの真似することは、全く信じられない話です。
しかし、一方のアメリカはもう変わってきています。
日本的経営みたいなことが、アメリカでもイギリスでも叫ばれてきているのです。
こんなときに日本がまだ以前のアメリカの真似することは、全く信じられない話です。
(JMA)
日本的経営をもっと世界に出していく必要があるのではないかということですよね。
(日覺)
そうです。アメリカは現にそうなってきているし、シリコンバレーもそうですよ。
(JMA)
日覺社長がそういった発信されるとおもしろくなるのではとも強く感じています。
(日覺)
日本でも外国でも、いろいろなところで発信していますよ。
経営者に必要なリーダーシップとは?
(JMA)
本日の受講者の皆さんは役員になられた方ばかりですが、早ければ5年後、遅くとも10年後には、その中から各社の社長になられる方がいると思います。
そういった先を見据えて、応援のメッセージをお願いします。
そういった先を見据えて、応援のメッセージをお願いします。
(日覺)
経営者に必要なのはリーダーシップだとよく言われるのですが、リーダーシップとは、現場を理解するためにみんなの言うこと聞くことなのです。
リーダーシップだから経営の本を読んだり、ああしなさい、こうしなさいと言ったりしても、徹底的に現場を知る、現場の人の考えていることを理解することにはおよびません。
現場にはもう答えがあり、方向性が決まりますので、それをしっかりとみんなにベクトルを合わせ、やっていくために引っ張っていくことが1番大切だと思います。
本読んだりとか、偉そうな人や経営コンサルタントが言ったりしていることを、ただそのまま言って行う人がいますが、現場の全てにはそれなりの理由があるのです。
そこをしっかり聞いてあげないといけません。
そうすることによって、なぜそうしているのかとか、それは元々違うのではないかとか、間違った考えを起こす原因は何なのかとか、そういうことがわかります。
それがしっかりわかったなら、あとはもうその現場に必要なことを思う存分やればいいですよね。
せっかく生まれてきて1度しかない人生なのだから、自分の思う通りにやったほうがいいのではないかということです。
今の経営スタイルなどもそうですけど、自分は現場を見てこう思うのに、それと違うことを言われ、おかしいと思うけれど、まあ、言われるから仕方ないといってやっていたのでは納得できないでしょう。
やはり自分で納得できることをやらないとダメだと思います。
間違っていても納得していたらいいのですよ。
リーダーシップだから経営の本を読んだり、ああしなさい、こうしなさいと言ったりしても、徹底的に現場を知る、現場の人の考えていることを理解することにはおよびません。
現場にはもう答えがあり、方向性が決まりますので、それをしっかりとみんなにベクトルを合わせ、やっていくために引っ張っていくことが1番大切だと思います。
本読んだりとか、偉そうな人や経営コンサルタントが言ったりしていることを、ただそのまま言って行う人がいますが、現場の全てにはそれなりの理由があるのです。
そこをしっかり聞いてあげないといけません。
そうすることによって、なぜそうしているのかとか、それは元々違うのではないかとか、間違った考えを起こす原因は何なのかとか、そういうことがわかります。
それがしっかりわかったなら、あとはもうその現場に必要なことを思う存分やればいいですよね。
せっかく生まれてきて1度しかない人生なのだから、自分の思う通りにやったほうがいいのではないかということです。
今の経営スタイルなどもそうですけど、自分は現場を見てこう思うのに、それと違うことを言われ、おかしいと思うけれど、まあ、言われるから仕方ないといってやっていたのでは納得できないでしょう。
やはり自分で納得できることをやらないとダメだと思います。
間違っていても納得していたらいいのですよ。
そこにある事実の重さとは?
(JMA)
現場に行って納得していればそれでいいですよね。
(日覺)
現場に行き、しっかり納得し、それをしっかり自分でやるということだと思います。
(JMA)
「現場に行こう」という今日のご講演から一貫したメッセージですね。
(日覺)
シンプルにずっと一貫しています。
本に書いてあることが当てはまることもあると思いますが、体系的にまとめたものは一般論であって、個々に適応すると、すこし矛盾が生じると思います。
そこにあるのが事実なのですから、やはり現場の方が言うことは重みが違いますよね。
こうしろと言われてもそうならないのは事実なのですから、なるはずだと言ってもお話にならないですよね。全ては現場です。
本に書いてあることが当てはまることもあると思いますが、体系的にまとめたものは一般論であって、個々に適応すると、すこし矛盾が生じると思います。
そこにあるのが事実なのですから、やはり現場の方が言うことは重みが違いますよね。
こうしろと言われてもそうならないのは事実なのですから、なるはずだと言ってもお話にならないですよね。全ては現場です。
(JMA)
本当にどうもありがとうございました。
※日覺氏には、第57回新任執行役員セミナーでのご講演後、本インタビューにご協力いただきました。