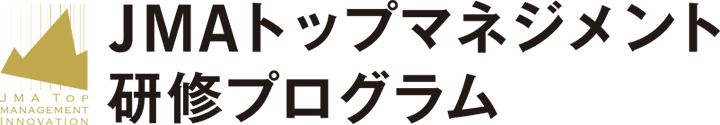ライフネット生命保険株式会社 代表取締役会長 出口 治明氏に、これから会社を担う役員の方々に対するメッセージや、経営者として心がけること、学ぶ姿勢についてなどお伺いいたしました。(※敬称略)
インタビュアー:一般社団法人日本能率協会 井上
一番理想的な上司とは?
(JMA)
出口会長は、前職は大手企業にお勤めでしたが、当然若い頃には上司がいて、その時にいい上司と感じておられたのは、どんな方でしたか?
(出口)
自然についていける上司が一番です。
(JMA)
会長からご覧になられても、自然についていける方がという。
(出口)
この人だったらついていこうか、となる人が一番いい上司だと思います。
(JMA)
本を拝読していますと、かなり大胆なというか、破天荒な上司がいらっしゃったようなことが書かれていましたけれども。
(出口)
いろいろなタイプの人がいるので、理想的な上司はそもそもいるはずがないのです。
(JMA)
形はないですね。
(出口)
人間は皆違うので、上司といってもさまざまだと思いますが、みんながついていく人。
「あの人好きだ」とか「あれだけ賢かったら仕方がない」「あれだけ頑張って仕事に打ち込んでいたら仕方がないな」と思って、人が自然についていく上司がやはり理想です。
「あの人好きだ」とか「あれだけ賢かったら仕方がない」「あれだけ頑張って仕事に打ち込んでいたら仕方がないな」と思って、人が自然についていく上司がやはり理想です。
(JMA)
その後、会長が還暦の頃にライフネットを立ち上げられたわけですが、周りからするとかなり思い切ったお話だったと思いますけれども、随分と年下の部下の方もついていかれたとお聞きしています。
(出口)
おかげさまで会社が続いているということは、なんやかんやと言いながらも、ついてきたからです。
だからやはり上に立つ者はですね、基本的に何もしなくても、下が勝手に動いてくれる上司が最高の上司だと思いますね。
上司というのは機能ですから、チームの能力を最大限に発揮することが上司の仕事です。
上司だから偉いというわけではなく、何もしなくても、皆が一生懸命頑張って仕事をしてくれる上司というのが、永遠の理想ではないでしょうか。
だからやはり上に立つ者はですね、基本的に何もしなくても、下が勝手に動いてくれる上司が最高の上司だと思いますね。
上司というのは機能ですから、チームの能力を最大限に発揮することが上司の仕事です。
上司だから偉いというわけではなく、何もしなくても、皆が一生懸命頑張って仕事をしてくれる上司というのが、永遠の理想ではないでしょうか。
社長の仕事とは?
(JMA)
会長の著書である「任せ方の教科書」の中に、クビライさんの話がありますけれども、大人数がいても、全員の配置も含めて考え行動をしていると、どんな大きな組織も動かせると。
(出口)
モンゴルは十進法が有名ですが、人間がきちんと見ることができるのは10人ぐらいだという経験則に基づいています。
会社のトップの方の中には、「たまには若い者の言うことも聞かないといけない」などと言って、若い社員10人や20人とお昼を食べたりして、そのようなことを自慢気に語っている方がいらっしゃいますが、いくら気楽な雰囲気だったとしても、なかなか若い社員は差し障りのないことしか言えませんから、もしもクビライが聞いたら、「そんな暇があるなら、自分たちの役員をしっかり見なさい」と言うと思います。
会社のトップの方の中には、「たまには若い者の言うことも聞かないといけない」などと言って、若い社員10人や20人とお昼を食べたりして、そのようなことを自慢気に語っている方がいらっしゃいますが、いくら気楽な雰囲気だったとしても、なかなか若い社員は差し障りのないことしか言えませんから、もしもクビライが聞いたら、「そんな暇があるなら、自分たちの役員をしっかり見なさい」と言うと思います。
(JMA)
トップがいて、その下に10人の役員がいて、さらにその下に部長がいて、またさらにその下にいる人たちとトップがいきなり会っても、ということですね。
(出口)
ちょっかいを出しても、そのようなことは単なる自己満足ではないかと。
(JMA)
その間にいる、それぞれの責任を持つリーダーの権限を飛ばしてしまうということにもなるわけですよね。
(出口)
その通りです。
(JMA)
そうすると、任されたはずの中間管理職の方たちはどう思うのか?
(出口)
「俺のことが不安だから若い者に告げ口させているのかな」とそのように思ったら、かえって逆効果になるので。
(JMA)
やはりそういうこともトップが認識をして、「俺は10人の隊長を見る」と。
(出口)
「俺は役員だけを見る」、それが社長の仕事です。
上に立つ者が持つべきものとは?
(JMA)
あとは役員に徹底的に任せる、範囲を決めて任せるということですね。
(出口)
もし不都合があるのだったら、クビを切ればいい。
ちょっかいを出すのではなくて、選んだ自分が悪かったと思ってクビを切ればいいんです。
個人商店のような発想ですけれども、上に立てばオールマイティだと思って、自分はなんでも言えると思ってしまうのですけれども、一度あげた権限は取り返せないのです。
それが組織の要点なので、「お前にこの範囲の決裁は任せた」と言ったら、それは取り戻せません。
ちょっかいを出すのではなくて、選んだ自分が悪かったと思ってクビを切ればいいんです。
個人商店のような発想ですけれども、上に立てばオールマイティだと思って、自分はなんでも言えると思ってしまうのですけれども、一度あげた権限は取り返せないのです。
それが組織の要点なので、「お前にこの範囲の決裁は任せた」と言ったら、それは取り戻せません。
(JMA)
さらに自分がそこでちょっかいを出したら、権限を与えたことにはならないですね。
(出口)
なりません。
与えてもらったほうも不安になるから、今度は全部お伺いを立てるようになります。すると忙しくなるだけで、ろくな仕事ができなくなる。
例えばそれがボールペンであったとしても、誰かにあげたら、もう取り返せないでしょう?
与えてもらったほうも不安になるから、今度は全部お伺いを立てるようになります。すると忙しくなるだけで、ろくな仕事ができなくなる。
例えばそれがボールペンであったとしても、誰かにあげたら、もう取り返せないでしょう?
(JMA)
はい、できません。
(出口)
「やはり俺が使いたいから返せ」と言ったら変でしょう。
「上司が最大の労働条件」という言葉がありますが、人が働く条件の100%は上司であり、上司は労働条件のすべてです。
上に立つ者は、やはりそのような秩序の感覚や権限の感覚を持ち、チームを率いるファンクションをきちんと考えなければいけないと思います。
「上司が最大の労働条件」という言葉がありますが、人が働く条件の100%は上司であり、上司は労働条件のすべてです。
上に立つ者は、やはりそのような秩序の感覚や権限の感覚を持ち、チームを率いるファンクションをきちんと考えなければいけないと思います。
(JMA)
考えて行動をして、任せたものは任せると。
(出口)
そうすれば意気に感じて頑張るじゃないですか。
(JMA)
そうですね。
もちろん結果も求めていかなければということも判断して。
もちろん結果も求めていかなければということも判断して。
(出口)
だから任せたと。
そのかわり1年後には「きちんとこれだけの税金を持って来いよ」、「これだけの獲物を持って来いよ」ということをイメージすればいいのです。
そのかわり1年後には「きちんとこれだけの税金を持って来いよ」、「これだけの獲物を持って来いよ」ということをイメージすればいいのです。
(JMA)
そうですね、はっきりとしたイメージを。
(出口)
結果は、1年が経った時にきちんと鹿2匹という獲物を持って来るかどうかで判断をすればいいので、途中で「お前、弓の使い方がだめではないか」とか、そういうことを言ってはいけないのです。
プレイヤーとマネージャーの役割の違いとは?
(JMA)
とてもわかりやすいお話ですよね。
今日ご参加されているのは、実は執行役員になられたばかりの方々で、お聞きしてみたところ、優秀なプレイヤーの方が多いようでした。
今日ご参加されているのは、実は執行役員になられたばかりの方々で、お聞きしてみたところ、優秀なプレイヤーの方が多いようでした。
(出口)
今日はプレーイング・マネージャーの話をしようと思います。
(JMA)
まだ執行役員になられたばかりで、優秀なプレイヤーと、会社の代表としての管理者、マネージメントの違いの端境期にいるような方もいらっしゃいますので、そのさわりだけでもお話いただけたらと思います。
(出口)
そうですね、お話しようとは思いますが。
(JMA)
先程のクビライの話もそうですけれども、いつまでも自分がプレイしている場合じゃないですよね。
(出口)
(中日ドラゴンズの)谷繁も、ほとんどキャッチャーマスクをかぶっていなかった。
マスクをかぶるとピッチャーに集中するので、全体が見えなくなる。
キャッチャーのポジションでミットを構えていると、ピッチャーが投げるボールに全力集中しなければいけないので、ゲーム全体が見えなくなってしまうのです。
マスクをかぶるとピッチャーに集中するので、全体が見えなくなる。
キャッチャーのポジションでミットを構えていると、ピッチャーが投げるボールに全力集中しなければいけないので、ゲーム全体が見えなくなってしまうのです。
(JMA)
ベンチの人間の士気の高さもわかりませんね。
(出口)
わかりません。
(JMA)
役割が違うのは当然のことですよね。
(出口)
もちろん小さい会社などでは、仕方なくプレーイング・マネージャーも必要ですが、プレイヤーとマネージャーは、まったく別の能力です。
今、「私の履歴書」で釜本邦茂さんが書いていますけれど、シュートを入れるという能力と、ゲーム全体を見て、選手を入れ替えて、試合に勝つという能力は別です。
今、「私の履歴書」で釜本邦茂さんが書いていますけれど、シュートを入れるという能力と、ゲーム全体を見て、選手を入れ替えて、試合に勝つという能力は別です。
(JMA)
釜本選手は偉大な成績を残していらっしゃいますけれども、釜本監督は相当苦労されたと聞いております。
(出口)
有名な選手ほど、自分がこれだけできるということがわかっているので、できない選手にはイライラするのです。
(JMA)
なぜできないと。
でもそうじゃないですよね。
でもそうじゃないですよね。
(出口)
人は皆違うので。
それはつまり、プレイヤーとマネージャーはまったく違うということを理解しなければ。
それはつまり、プレイヤーとマネージャーはまったく違うということを理解しなければ。
(JMA)
わかっているけれどもできないことも含めて、改めてそれをきちんと自分で理解して。
(出口)
理解しなければ生産性も能率も上がらない、皆がくたびれるだけだと。
プレイヤーに必要な意識の転換とは?
(JMA)
少しやわらかなほうでいくと、会長のお言葉の中に「人間ちょぼちょぼ主義」というのがありまして、実は今回のメンバーの執行役員の方でも、うちの部隊に優秀な部下がいないとおっしゃる方が。
(出口)
執行役員といっても、人間はみんな基本的に「愚か」なので。
(JMA)
その勘違いもしてはいけませんよね。
(出口)
人間はみんな「愚か」だというところをわきまえれば、いろいろなことが見えてきます。
例えば私が100点の仕事ができるとして、3人いる部下は40点の仕事しかできないとする。
でも3人いたら120点の仕事なので。
例えば私が100点の仕事ができるとして、3人いる部下は40点の仕事しかできないとする。
でも3人いたら120点の仕事なので。
(JMA)
あ、負けました。
(出口)
単純に言えばそのようなことです。
100点の自分がフルに頑張るよりも、40点でも3人を目一杯働かせたほうが、120点でチームとしては上がります。
100点の自分がフルに頑張るよりも、40点でも3人を目一杯働かせたほうが、120点でチームとしては上がります。
(JMA)
当然その意識転換も必要ですよね。
もしかすると、優秀なプレイヤーほど、それができにくいのかもしれませんね。
もしかすると、優秀なプレイヤーほど、それができにくいのかもしれませんね。
(出口)
できないことが多いです。
(JMA)
100点の自分40点の部下、その違いを意識してしまうということがあるかもしれませんね。
(出口)
だから普通の人のほうがいいと思います。
プレイヤーとしては普通だけれども、人の気持ちが分かるとか。
プレイヤーとしては普通だけれども、人の気持ちが分かるとか。
(JMA)
会長は読売新聞でも書評を書かれておられますし、すでにもうこれだけのキャリアを残していらっしゃいますけれども、ご自身では今お話されたようなこと、例えば日本生命に入社をされた当時から、その感覚は持っておられましたか?
(出口)
それは段々と、「人」「本」「旅」通じて勉強しきました。
(JMA)
やはり20歳のころからどんどんと経験を積まれて?
(出口)
いろいろな人の話を聞いたり、本を読んだり、さまざまなところへ行って、いろいろなものを見ることで、「やっぱり人間は愚かだな」ということがわかってくるし、プレイヤーとマネージャーは違うなということもわかってきました。
書かれていないから、本を読んだだけではわからないこともありますよね。途中で少し痛い目にあったりもして、いろいろな経験をしながらわかってくるものでです。
書かれていないから、本を読んだだけではわからないこともありますよね。途中で少し痛い目にあったりもして、いろいろな経験をしながらわかってくるものでです。
(JMA)
当然これまで痛い目にもあわれているし、失敗もされているということですね。
(出口)
それはもう山ほど。
(JMA)
中には会長を教養の達人という人もいますけど。
(出口)
年を取っているから、人より少し雑学に長けているぐらいのものです。
人を育てる為に必要なこととは?
(JMA)
現在のライフネットの社長は、会長とは30歳程も離れた年齢でいらっしゃいますが、やはり社長を任せているということは、それなりの人間観などをお持ちだという認識があっての任命だったのでしょうか。
(出口)
それは逆です。
まだまだなので、社長の椅子を与えて大きくしたいという発想のほうが正しいかもしれません。
まだまだなので、社長の椅子を与えて大きくしたいという発想のほうが正しいかもしれません。
(JMA)
だからこそ、社長を任せたということなのですね。
(出口)
だって責任を与えないと、素振りばかりやっていても、試合に出さないと勝負強いのかどうかわからないじゃないですか。
プロ野球でも、素質がある若い人は少し2軍でやらせてみて、見どころがあったら1軍に引き上げてやらせてみる。
そうして名選手になっていくので、素振りばかりやっている選手に4番を打たせるっていってもできるはずがない
山本五十六も言っているように、「やらせてみて初めてわかる」「人が育つ」と。
プロ野球でも、素質がある若い人は少し2軍でやらせてみて、見どころがあったら1軍に引き上げてやらせてみる。
そうして名選手になっていくので、素振りばかりやっている選手に4番を打たせるっていってもできるはずがない
山本五十六も言っているように、「やらせてみて初めてわかる」「人が育つ」と。
(JMA)
先程の話につながりますけれども、執行役員の方も、部下の出来云々と言う前に、まずは自分のことを権限も含めてきちんと区分けして、任せてやらせてみるということが第一歩であるのかもしれませんね。
(出口)
そうです。人を育てるのは、任せることしかできません。
口を挟んで育つはずがない。口うるさい怖いおっさんだから、迷ったら自分で判断せずになんでも聞こうということにもなりますから、そのようなことでは余計に育たなくなる。
口を挟んで育つはずがない。口うるさい怖いおっさんだから、迷ったら自分で判断せずになんでも聞こうということにもなりますから、そのようなことでは余計に育たなくなる。
(JMA)
部下がいつも判断を仰いだり、顔色をうかがったり、過剰な気遣いばかりをするようになるという話も、よくお聞きするのですけれども。
(出口)
人が育つどころか、だんだんと退化していきます。
(JMA)
それはもしかしたら、上に立つ人のところに原因があるということですね。
(出口)
もちろんそうです。
若者がだらしない、子どもがだらしないのは、大人がだらしないからで、ロールモデルなので、すべては上に原因があります。
若者がだらしない、子どもがだらしないのは、大人がだらしないからで、ロールモデルなので、すべては上に原因があります。
(JMA)
すべては管理職ということですね。
(出口)
ええ。監督が「アホ」だったら野球はできないのです。
(JMA)
会長が使われる「アホ」という言葉は、いつもピンポイントで届きます。著書にもありましたけれど、長い時代を生き延びてきた古典を読んで、わからなければ自分が「アホ」だと思うと。
ただし、まだ歴史の鑑識がぬけていない新著に関しては、わからないのは著者が悪いというのも非常にわかりやすくて。
ただし、まだ歴史の鑑識がぬけていない新著に関しては、わからないのは著者が悪いというのも非常にわかりやすくて。
(出口)
古典がなぜ難しいかといえば、時代環境が違うからです。
それを理解しなければ難しいですけれど、今は時代環境が一緒で、皆アベノミクスの中で生きていますので、書いてあることがわからなければ、それは著者が「アホ」なのか、わざと難しい言葉を作って「俺は偉いよ」って言っているだけの、やはりこれも一種の「アホ」なんです。
それを理解しなければ難しいですけれど、今は時代環境が一緒で、皆アベノミクスの中で生きていますので、書いてあることがわからなければ、それは著者が「アホ」なのか、わざと難しい言葉を作って「俺は偉いよ」って言っているだけの、やはりこれも一種の「アホ」なんです。
(JMA)
とてもわかりやすいです。
(出口)
そういう本は、読むだけ時間の無駄。
(JMA)
だからなのか、会長が読売新聞で書評されている本の多くは、歴史に関係するものが多いような気がします。
(出口)
人間はみんな違います。
歴史に残っているというのは、面白いか、ユニークなことをしたからなのであって、面白くないものは書かないでしょう? 面白いから書くわけです。
歴史に残っているというのは、面白いか、ユニークなことをしたからなのであって、面白くないものは書かないでしょう? 面白いから書くわけです。
成長していく為に失ってはならないこととは?
(JMA)
今日来られているのは執行役員ですけれども、今後はもっと重い責任を担う取締役や専務となり、いずれは社長にということを期待されている方々です。
最後にあらためて、彼らに対してメッセージをいただけたらと思うのですが。
最後にあらためて、彼らに対してメッセージをいただけたらと思うのですが。
(出口)
「人」「本」「旅」で勉強し続けることだと思います。
人間はほうっておいたら「愚か」なままだけれども、「人」「本」「旅」で勉強したら、少しはマシになるかもしれない。
それ以外にはないと思います。
人間はほうっておいたら「愚か」なままだけれども、「人」「本」「旅」で勉強したら、少しはマシになるかもしれない。
それ以外にはないと思います。
(JMA)
偶然ですが、昨日の、経営者から最後にいただいたメッセージも「学ぶ」ということでした。
まったく同じでございますね、当然かもしれませんけれども。
だから会長は、60歳からでも起業されて、さらにどんどん新しいことを学んでいらっしゃるというわけですね。
まったく同じでございますね、当然かもしれませんけれども。
だから会長は、60歳からでも起業されて、さらにどんどん新しいことを学んでいらっしゃるというわけですね。
(出口)
世の中には、まだまだ知らないことがたくさんありますし、世界にはいろいろな面白いことがあって、その中で自分の知っていることは、0.001%にも満たない。いろいろなことを知りたいという気持ちを失ったら、おしまいだと思います。
(JMA)
会長にそうおっしゃられると、何も言えません。
(出口)
このインタビューは、どこかにまとめられるのですか?
実は広報から下品な言葉は使わないでくださいと言われているもので…。
実は広報から下品な言葉は使わないでくださいと言われているもので…。
(JMA)
そうですか。
ただ聞き手にとっては、とてもインパクトがあってわかりやすい話として伝わると思いますが。
ただ聞き手にとっては、とてもインパクトがあってわかりやすい話として伝わると思いますが。
(出口)
話し言葉ではいいけれど、あまり下品だとうちの広報に叱られるので。
(JMA)
会長も叱られたりするのですね。
(出口)
もう少し年齢や立場をわきまえてくださいと言われます。
(JMA)
活字にすると印象がまた違いますよね。
会長が、まだまだ自分の知識は0.00001%などとおっしゃると、もう世の中の人全員が、まだまだ勉強しないといけないなと感じるのではないかと思います。
会長が、まだまだ自分の知識は0.00001%などとおっしゃると、もう世の中の人全員が、まだまだ勉強しないといけないなと感じるのではないかと思います。
(出口)
それはそうです、地球は大きいので。
この前、驚いたことがあったのですけれど、海って1万メートルもあるので、広いでしょう? 深いでしょう? 海の体積って地球の何分の1くらいだと思います?
この前、驚いたことがあったのですけれど、海って1万メートルもあるので、広いでしょう? 深いでしょう? 海の体積って地球の何分の1くらいだと思います?
(JMA)
20分の1くらいですか?10分の1?
(出口)
700分の1です。
(JMA)
海の表面ですね、そういうことですね。
(出口)
僕も最初、50分の1とか100分の1ぐらいかなと。
知らなかったので、いかに無知かということを反省して。
知らなかったので、いかに無知かということを反省して。
(JMA)
今日は出口会長のお話が聞けるのを、皆さんすごく楽しみにしていらっしゃいます。
会長の本も何冊か置かせていただいて、皆さんに見てもらっていますので。
会長の本も何冊か置かせていただいて、皆さんに見てもらっていますので。
(出口)
ありがとうございます。
(JMA)
今日はどうもありがとうございました。
※出口氏には「新任執行役員セミナー」にご登壇いただきました。