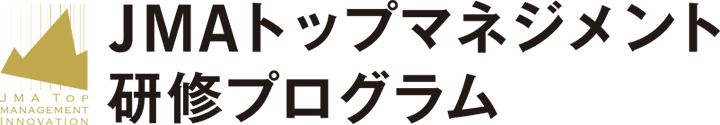帝人株式会社 取締役会長 大八木 成男氏に、これから会社を担う役員の方々に対するメッセージや、社員に挑戦させることの大切さ、経営者が心がけること、などについてお伺いいたしました。
インタビュアー:一般社団法人日本能率協会 久保田
執行役員になって大切なこととは?
(久保田)
本日は3点ほどうかがいたいことがあります。
まず1点目は本日講演していただいた感想です。
2点目は大八木様が新任の執行役員になったとき、それから社長になられたとき、それぞれどのように考え、ご自身をブラッシュアップされてきたかについてです。
最後の3点目は、今日の受講生は新任の執行役員ばかりなのですが、そういった方々への応援メッセージやエールをいただきたいと思っています。
まずは本日の感想からお願いします。
まず1点目は本日講演していただいた感想です。
2点目は大八木様が新任の執行役員になったとき、それから社長になられたとき、それぞれどのように考え、ご自身をブラッシュアップされてきたかについてです。
最後の3点目は、今日の受講生は新任の執行役員ばかりなのですが、そういった方々への応援メッセージやエールをいただきたいと思っています。
まずは本日の感想からお願いします。
(大八木会長)
受講生の皆さんともそれぞれの会社で責任ある立場に就かれていますから、あまり面白くない話かもしれませんが、最後まで大変熱心に聞いてくださいました。
その点にまず、感謝を申しあげます。
質問にも出てきましたが、ご自分の会社で相当の課題や問題をそれぞれ抱えているようです。
その点に関し、私の話の中でヒントになる点がいくつかあったと思います。
質問も積極的にしていただきました。
また執行役員としてこれから成長していこうという気構えを、すごく感じました。
総じて今回の受講生は非常に前向きな方が集まっているように見受けられました。
当然のことですが、組織の中で役員にはなかなかなれるものでありません。
皆さんが執行役員になったということは、少なくとも過去に大きな業績を残しているはずです。
その業績が既存のビジネスを守るだけではなく、何かを新たに産み出すものか、あるいは産み出す過程にあるものだとしたら、執行役員のその人に会社の期待が集まっていると思います。
今は1段階成し遂げたという満足感が、きっとあるだろうと思いますが、ただ、ここからのスタートが大事です。
執行役員になると、当面は自分の専門的な知識や経験がある場所でリーダーとして活躍することになるでしょう。
ところがここから先、組織のリーダーとなるためには、さらにいくつもステップを越えなければならないのです。
常に自分の事業も他人の事業に対しても的確な批判精神を持ち、見ていかなければ、そのステップを越えることは難しいと思います。
その点にまず、感謝を申しあげます。
質問にも出てきましたが、ご自分の会社で相当の課題や問題をそれぞれ抱えているようです。
その点に関し、私の話の中でヒントになる点がいくつかあったと思います。
質問も積極的にしていただきました。
また執行役員としてこれから成長していこうという気構えを、すごく感じました。
総じて今回の受講生は非常に前向きな方が集まっているように見受けられました。
当然のことですが、組織の中で役員にはなかなかなれるものでありません。
皆さんが執行役員になったということは、少なくとも過去に大きな業績を残しているはずです。
その業績が既存のビジネスを守るだけではなく、何かを新たに産み出すものか、あるいは産み出す過程にあるものだとしたら、執行役員のその人に会社の期待が集まっていると思います。
今は1段階成し遂げたという満足感が、きっとあるだろうと思いますが、ただ、ここからのスタートが大事です。
執行役員になると、当面は自分の専門的な知識や経験がある場所でリーダーとして活躍することになるでしょう。
ところがここから先、組織のリーダーとなるためには、さらにいくつもステップを越えなければならないのです。
常に自分の事業も他人の事業に対しても的確な批判精神を持ち、見ていかなければ、そのステップを越えることは難しいと思います。
執行役員に必要な視点を持つ方法とは?
(久保田)
批判の精神を持ち、自分の事業以外のところも見るということは、1つ視点を上げることにもなりますね。
執行役員になればそういう視点を持たなければならないのでしょうね。
大八木様はそういう視点を持てるよう自分で心がけてきたと思います。
具体的にはどんなことをやってこられたのでしょうか。
執行役員になればそういう視点を持たなければならないのでしょうね。
大八木様はそういう視点を持てるよう自分で心がけてきたと思います。
具体的にはどんなことをやってこられたのでしょうか。
(大八木会長)
これは自分が心がけるというよりは、そうできる場所を会社の中につくる必要があります。
執行役員会議とか、要するに全グループのいろいろな職種の者が集まる場所ですね。
私どもの会社では、昔は執行役員の数はもっと多かったのですが、今はだいたい30人ぐらいの数の人を集めて勉強する機会があります。
執行役員会議ではいろいろな講師を呼んで勉強する一方、ディスカッションもできるようになっています。
同じ執行役員でもステップが上がると、戦略会議などのメンバーにもなります。
そういう場を通じて新しい知見や考え方の中で揉まれ段々と目が開いてくるものです。
仏像の目が開眼するような感じでしょうか。
そういう機会がないと、「勉強しろ」といったところで、なかなか難しいと思います。
執行役員は実務に追われ外へ出て行って勉強する機会もあまりありませんので、会社の中で、自分で鍛えていくしかないと思います。
だから、経営のトップがそういう場を作ることがとても大事になってきます。
例えば、組織横断的な執行役員会議や執行役員研修会、夏の役員合宿などです。
会社としてはそういう場所で全員の姿をきちんと見えるようにしておく必要があるでしょう。
その中でさらに特定の人材を育てようとするなら、会社全体が鳥瞰できる部署につく方がいいと思います。
例えば、社長室や計画部がその1つです。
チーフインフォメーションオフィサー(CIO)やチーフテクノロジーオフィサー(CTO)、マーケティングオフィサー(MO)、フィナンシャルオフィサー(FO)といった機能のトップに据えるのも1つの方法になります。あるいは人事(CHO)もそうです。
そうしたポジションから全社を見ることが大切です。
全社が見るようになると、事業は外部との戦いであることが見えてきます。
今度は他の会社と情報交換するなどして自社の位置付けや優劣などを理解していきます。
触覚が働くようになると、一段上からものが見えてきます。
ここでそうなれるかどうかが別れ道です。
できる人には、次にはプロジェクトを持たせます。リーダーの誕生です。
できればプロジェクトは既存のビジネスではなく、新しくチャレンジする一般的に新規事業といわれるプロジェクトを任せることが好ましい。
その中でどこまで本人がやれるかが、次の別れ道です。
プロジェクトリーダーから部門長や本部長になったら、担当領域をガラッと変えてしまうのも手です。
ビジネス領域によりモデルは全く違うことが多いので、担当領域を変えて目覚めさせるわけです。
そうすると、どんなビジネスモデルが最も儲かるのか、よく分かります。
結果として、ビジネスモデルを変えたら収益が全く違うことに、気づいてくれるとしめたものです。
執行役員会議とか、要するに全グループのいろいろな職種の者が集まる場所ですね。
私どもの会社では、昔は執行役員の数はもっと多かったのですが、今はだいたい30人ぐらいの数の人を集めて勉強する機会があります。
執行役員会議ではいろいろな講師を呼んで勉強する一方、ディスカッションもできるようになっています。
同じ執行役員でもステップが上がると、戦略会議などのメンバーにもなります。
そういう場を通じて新しい知見や考え方の中で揉まれ段々と目が開いてくるものです。
仏像の目が開眼するような感じでしょうか。
そういう機会がないと、「勉強しろ」といったところで、なかなか難しいと思います。
執行役員は実務に追われ外へ出て行って勉強する機会もあまりありませんので、会社の中で、自分で鍛えていくしかないと思います。
だから、経営のトップがそういう場を作ることがとても大事になってきます。
例えば、組織横断的な執行役員会議や執行役員研修会、夏の役員合宿などです。
会社としてはそういう場所で全員の姿をきちんと見えるようにしておく必要があるでしょう。
その中でさらに特定の人材を育てようとするなら、会社全体が鳥瞰できる部署につく方がいいと思います。
例えば、社長室や計画部がその1つです。
チーフインフォメーションオフィサー(CIO)やチーフテクノロジーオフィサー(CTO)、マーケティングオフィサー(MO)、フィナンシャルオフィサー(FO)といった機能のトップに据えるのも1つの方法になります。あるいは人事(CHO)もそうです。
そうしたポジションから全社を見ることが大切です。
全社が見るようになると、事業は外部との戦いであることが見えてきます。
今度は他の会社と情報交換するなどして自社の位置付けや優劣などを理解していきます。
触覚が働くようになると、一段上からものが見えてきます。
ここでそうなれるかどうかが別れ道です。
できる人には、次にはプロジェクトを持たせます。リーダーの誕生です。
できればプロジェクトは既存のビジネスではなく、新しくチャレンジする一般的に新規事業といわれるプロジェクトを任せることが好ましい。
その中でどこまで本人がやれるかが、次の別れ道です。
プロジェクトリーダーから部門長や本部長になったら、担当領域をガラッと変えてしまうのも手です。
ビジネス領域によりモデルは全く違うことが多いので、担当領域を変えて目覚めさせるわけです。
そうすると、どんなビジネスモデルが最も儲かるのか、よく分かります。
結果として、ビジネスモデルを変えたら収益が全く違うことに、気づいてくれるとしめたものです。
(久保田)
きょうの話にも出てきましたが、課長に他の部門の事業を勉強させているのもそのためでしょうか。
(大八木会長)
そうです。
グルーバルの競争の中で、ビジネスモデルを変えない限り、生きられないことは、もう明白になってきています。
きょうも申し上げましたが、優れたスマートチャネルキラーがたくさん登場してきていますから。
これからの時代はITを専門とし、人工知能まで扱うような人たちがやってきます。
およそ旧来のやり方ではとても太刀打ちできないでしょう。
逆に彼らの力を利用しながら事業を展開する方向に、事業形態を変えていかなければなりません。
事業や製品の複合化とか融合化とかいうことが見えてくるはずです。
それに気づいて欲しいですね。
グルーバルの競争の中で、ビジネスモデルを変えない限り、生きられないことは、もう明白になってきています。
きょうも申し上げましたが、優れたスマートチャネルキラーがたくさん登場してきていますから。
これからの時代はITを専門とし、人工知能まで扱うような人たちがやってきます。
およそ旧来のやり方ではとても太刀打ちできないでしょう。
逆に彼らの力を利用しながら事業を展開する方向に、事業形態を変えていかなければなりません。
事業や製品の複合化とか融合化とかいうことが見えてくるはずです。
それに気づいて欲しいですね。
複合化に向かうきっかけとは?
(久保田)
御社の中で戦略を作るに当たり、複合化の方向に向かっているということですが、その方向性を導き出すプロセスで大八木様が取られた対応はどんなことでしょうか。
(大八木会長)
会社組織は往々にして、事業単位毎につくられていて、事業間、部門間、或いは海外と国内とに別れて、組織の壁があり情報の流通が不自由になっていることが多い訳で、組織の壁、人の心の中にある障壁、これを取り払う必要があります。組織単位を大括りに変える、人の心の融和を図ることが必要となります。
(久保田)
そういった方針を出すとき、作るときのプロセスで、大八木さんが心に留めていることややっていることがあったら、教えていただきたいのです。
(大八木会長)
市場の出口を意識した、組織改革と情報の共有システムをつくり上げることですね。
社内で相当に議論したあと、サプライチェーンの話が出てきたことがあるのですが、そこで気づきました。
私共の素材事業は、産業の上流で品質の良いものを大量生産し素材として販売することに注力してきました。
時代の経過と共に、新興国に技術が移転し品質面ではともかくコスト競争力では劣後する状況に追い込まれてきました。
サプライチェーンの上流に位置する生産メーカーが産業領域を問わず共通して経験してきたことです。
したがって、サプライチェーンをいかに上流から下流に向かって事業展開を図るかが大きな課題となります。
時の経過と共に、私共の技術の人たちがいろいろと苦労しているうちに、素材から部材をつくる技術プロセスを創り上げることができました。
今、環境問題から軽量化が課題になっていますでしょう。
炭素繊維の複合部材は、既存の金属素材より強くて軽い。
同様にプラスチックの複合部材も、既存の素材よりすごく強くて軽量化されている。
因みに、高速鉄道のガラス窓に使用されている樹脂はガラスの200倍の強度があり、重さは2分の1しかありません。
そういうものをもっと見つけようということになったわけです。
更にサプライチェーンの話があります。
従来の素材売りでは、利益を得たと思ったら、また失います。
景気のサイクルのみならず、新興国への産業移転により、収益が大幅に変動しますので経営の安定度を高めるためには、産業領域を変えるとかサプライチェーン上の位置を変える努力が必要です。
景気のサイクルに巻き込まれると企業成長の蓄積ができないことから、欧米のケミカル会社のトップはすごい努力をしています。
最先端を行ったのはデュポンです。
デュポンは250年の歴史がありますが、100年毎に主力事業を替えています。
TOPのエレン・クルマンさんはケミカル部門を離し、バイオと食物、中でも種子事業への取組みにポートフォリオを切り替えていきました。
会社の規模を保ちながら、中身を切り替えていく手段としてM&Aが活用されました。
1兆円規模のM&Aをやり、会社の規模を保ちながら、収益構造を変えていくことに乗り出したわけです。
これは誰もができるわけではありません。
事業ポートフォリオの変革には資金が要ります。
私共の場合は時間は少しかかりますが、サプライチェーン上の変革を視野に入れて、
既存の事業を捨てるのではなく、活かしながら、もっといろいろな材料を集め、融合、複合化をやっていったら、まだ先があると考えました。
中身を変えて違う生態系の中で生きる会社になろうというわけです。
この考えに沿って、今はプロジェクトも成長戦略と発展戦略に分けてやっています。
私の時代より更に進化しています。
社内で相当に議論したあと、サプライチェーンの話が出てきたことがあるのですが、そこで気づきました。
私共の素材事業は、産業の上流で品質の良いものを大量生産し素材として販売することに注力してきました。
時代の経過と共に、新興国に技術が移転し品質面ではともかくコスト競争力では劣後する状況に追い込まれてきました。
サプライチェーンの上流に位置する生産メーカーが産業領域を問わず共通して経験してきたことです。
したがって、サプライチェーンをいかに上流から下流に向かって事業展開を図るかが大きな課題となります。
時の経過と共に、私共の技術の人たちがいろいろと苦労しているうちに、素材から部材をつくる技術プロセスを創り上げることができました。
今、環境問題から軽量化が課題になっていますでしょう。
炭素繊維の複合部材は、既存の金属素材より強くて軽い。
同様にプラスチックの複合部材も、既存の素材よりすごく強くて軽量化されている。
因みに、高速鉄道のガラス窓に使用されている樹脂はガラスの200倍の強度があり、重さは2分の1しかありません。
そういうものをもっと見つけようということになったわけです。
更にサプライチェーンの話があります。
従来の素材売りでは、利益を得たと思ったら、また失います。
景気のサイクルのみならず、新興国への産業移転により、収益が大幅に変動しますので経営の安定度を高めるためには、産業領域を変えるとかサプライチェーン上の位置を変える努力が必要です。
景気のサイクルに巻き込まれると企業成長の蓄積ができないことから、欧米のケミカル会社のトップはすごい努力をしています。
最先端を行ったのはデュポンです。
デュポンは250年の歴史がありますが、100年毎に主力事業を替えています。
TOPのエレン・クルマンさんはケミカル部門を離し、バイオと食物、中でも種子事業への取組みにポートフォリオを切り替えていきました。
会社の規模を保ちながら、中身を切り替えていく手段としてM&Aが活用されました。
1兆円規模のM&Aをやり、会社の規模を保ちながら、収益構造を変えていくことに乗り出したわけです。
これは誰もができるわけではありません。
事業ポートフォリオの変革には資金が要ります。
私共の場合は時間は少しかかりますが、サプライチェーン上の変革を視野に入れて、
既存の事業を捨てるのではなく、活かしながら、もっといろいろな材料を集め、融合、複合化をやっていったら、まだ先があると考えました。
中身を変えて違う生態系の中で生きる会社になろうというわけです。
この考えに沿って、今はプロジェクトも成長戦略と発展戦略に分けてやっています。
私の時代より更に進化しています。
新任執行役員に最も重要な点とは?
(久保田)
これから新しい時代に役員になった方にとって、特に重要になる点はどこになるでしょうか。
大八木様がやられた会社をどう変えていくか、1度決めたことに固執せず毎年柔軟に変えていくようなことを進めるうえで、アドバイスがあれば教えてください。
大八木様がやられた会社をどう変えていくか、1度決めたことに固執せず毎年柔軟に変えていくようなことを進めるうえで、アドバイスがあれば教えてください。
(大八木会長)
やはり1番大事なのは胆力でしょう。 自分を信じて、己を、会社を、進化させる努力を続けなさいということです。
自分を信じないと、胆力は出てきません。
そのためには常に外部の人と付き合いをし勉強していくこと、そして自分を変えていかないといけません。
執行役員はリーダーだと言う認識が大切です。
では、リーダーとは何か、マネジャーとは違うのかについて考える良い機会だと思いますよ。
最近、私は人事のことを研究している慶應義塾大の先生から「なるほど」と思える話を聞きました。
「ドラッカーからの引用だ」とおっしゃっていましたが、「マネジャーとリーダーは違う」というのです。
びっくりしましたね。
マネジャーとはいろいろな条件の下で「いわれたこと」を最新のテクノロジーを使い、一定期間の間に100%成就させるのが仕事だというわけです。
つまりは管理です。
しかし、リーダーは「見えない道」を探していかないといけません。
一定の堅い意思を持ち、新しい道を切り開く心構えが必要なわけです。
そのときに桃太郎ではありませんが、部下に吉備団子をあげないと部下はついてきません。
これは戦国武将と同じですね。
鬼退治に行くとしても、褒美が絶対に必要なのです。
インセンティブを出しながら、仲間を作っていくということになるのでしょうか。
自分のフォロワーをきちんと育てるといった方が分かりやすいかもしれませんね。
マネジャーにするためには経営の基礎知識やツールを明快に教えなければいけません。
こと経営に入ったら徹底的に勉強することが必要です。
若かりし頃、私も他社の教育実習に派遣されて、3カ月間毎日テストを受けました。
80点以下が落第なので、毎日何百ページも読んで暗記していきます。
こうして過ごして卒業した時に、私の中に臨床医学や骨格学、薬の作用、副作用などありとあらゆることが全部記憶として残り、専門家と対等に話せるようになりました。
実務的な実習ですから、名刺の渡し方、目線、1分・3分・5分・10分話法、プレゼンテーション30分といった具合に学んでいきます。
訓練はストップウォッチで測ります。
オーバーしたら間違いなく失格です。
そういう訓練が終わったあと、なぜか自信が湧き出てきました。
やはり1番大事なのは胆力でしょう。 自分を信じて、己を、会社を、進化させる努力を続けなさいということです。
自分を信じないと、胆力は出てきません。
そのためには常に外部の人と付き合いをし勉強していくこと、そして自分を変えていかないといけません。
執行役員はリーダーだと言う認識が大切です。
では、リーダーとは何か、マネジャーとは違うのかについて考える良い機会だと思いますよ。
最近、私は人事のことを研究している慶應義塾大の先生から「なるほど」と思える話を聞きました。
「ドラッカーからの引用だ」とおっしゃっていましたが、「マネジャーとリーダーは違う」というのです。
びっくりしましたね。
マネジャーとはいろいろな条件の下で「いわれたこと」を最新のテクノロジーを使い、一定期間の間に100%成就させるのが仕事だというわけです。
つまりは管理です。
しかし、リーダーは「見えない道」を探していかないといけません。
一定の堅い意思を持ち、新しい道を切り開く心構えが必要なわけです。
そのときに桃太郎ではありませんが、部下に吉備団子をあげないと部下はついてきません。
これは戦国武将と同じですね。
鬼退治に行くとしても、褒美が絶対に必要なのです。
インセンティブを出しながら、仲間を作っていくということになるのでしょうか。
自分のフォロワーをきちんと育てるといった方が分かりやすいかもしれませんね。
マネジャーにするためには経営の基礎知識やツールを明快に教えなければいけません。
こと経営に入ったら徹底的に勉強することが必要です。
若かりし頃、私も他社の教育実習に派遣されて、3カ月間毎日テストを受けました。
80点以下が落第なので、毎日何百ページも読んで暗記していきます。
こうして過ごして卒業した時に、私の中に臨床医学や骨格学、薬の作用、副作用などありとあらゆることが全部記憶として残り、専門家と対等に話せるようになりました。
実務的な実習ですから、名刺の渡し方、目線、1分・3分・5分・10分話法、プレゼンテーション30分といった具合に学んでいきます。
訓練はストップウォッチで測ります。
オーバーしたら間違いなく失格です。
そういう訓練が終わったあと、なぜか自信が湧き出てきました。
(久保田)
なるほど。
(大八木会長)
知識と経験がない人はどんなに優れていても自信を持てません。
本当に内面ではそうです。
こうした基礎のうえでリーダーのあり方や戦略の作り方、更には経営者教育を進めます。
教える順番が大切です。
いきなり戦略論から入ってもだめです。
マネジャーとリーダー、経営者、その区分の違いをはっきり意識し、段階を踏んで教えていく必要があるでしょう。
本当に内面ではそうです。
こうした基礎のうえでリーダーのあり方や戦略の作り方、更には経営者教育を進めます。
教える順番が大切です。
いきなり戦略論から入ってもだめです。
マネジャーとリーダー、経営者、その区分の違いをはっきり意識し、段階を踏んで教えていく必要があるでしょう。
(久保田)
最後になりますが、新任の執行役員に向けて応援メッセージをお願いします。
(大八木会長)
1に健康、2に健康、3番目は気力ですね。頑張りましょう。
(久保田)
ありがとうございました。
※大八木氏には「新任執行役員セミナー」にご登壇いただきました。